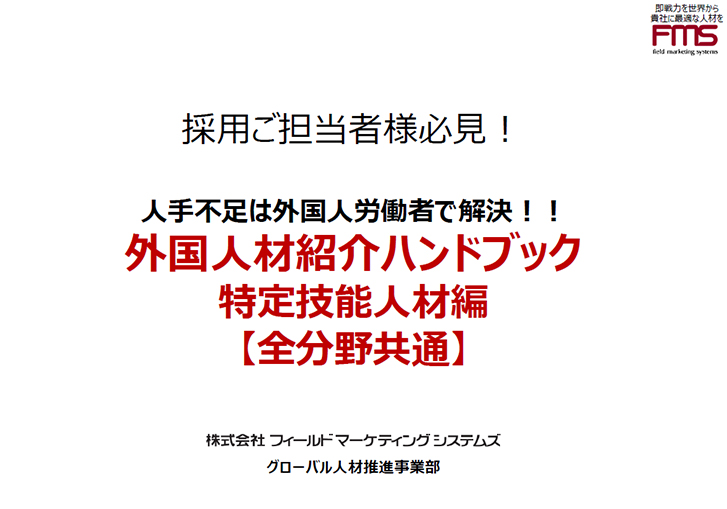人手不足が深刻化する中、飲食店や小売業、介護施設などで外国人採用を検討する企業が増えています。しかし、外国人採用には「在留資格」「就労ビザ」「外国人雇用状況届出書」など、関連する複数の手続きが必要になるため、流れを理解せずに進めると不法就労になりかねません。
そこで本記事では、外国人採用の流れと在留資格の種類、申請手続きの方法、費用の目安までわかりやすく解説します。
外国人採用を行う前に把握しておきたいこと

出典:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)丨厚生労働省
外国人採用を始める前に、外国人労働者の増加傾向や在留資格制度の概要を理解し、適切な雇用管理体制を整える必要があります。
厚生労働省の「外国人雇用状況届出制度」によると、外国人労働者数は年々増加しており、産業別の外国人労働者数も増加傾向にあることがわかりました。製造業を筆頭に、宿泊業、飲食サービス業、卸売業、小売業などの外国人労働者数も増加し続けています。
このように増え続ける外国人労働者について、採用企業は、在留資格の確認、外国人雇用状況届出の提出、労働条件通知書の作成、法的手続きを含めた確認と適切な対応が不可欠です。
外国人雇用は即戦力確保だけでなく、適切な支援体制を整えることで、企業の持続的成長にもつながります。
外国人採用の流れとは?採用フローを5ステップで整理

外国人採用は、一般的に以下の5ステップの流れで行われます。
- 1. 採用活動(求人・面接)
- 2. 雇用契約の締結
- 3. 在留資格の確認・申請
- 4. 入社手続き(保険・届出)
- 5. 雇用後の支援・更新管理
外国人採用がどのように進むのか、それぞれのステップについて具体的に解説します。
1. 採用活動(求人・面接)
外国人採用の第一歩は、適切な求人方法を選び、在留資格や就労ビザに合致した人材を見極めることです。
求人の手段には、ハローワークや人材紹介会社、登録支援機関などがあり、職種や必要なスキルに応じて選択できます。
特定技能外国人や外国人留学生を対象とする場合は、応募段階から在留カードの有効性や資格外活動許可の有無を確認しましょう。
採用活動を丁寧に行えば、その後の雇用契約や在留資格申請もスムーズに進み、外国人労働者との安定した雇用関係を築く基盤となります。
2. 雇用契約の締結
外国人労働者を採用する際は、雇用契約書や労働条件通知書を整備することで、在留資格に適合する労働条件を明示しましょう。
特定技能外国人や技能実習生を雇用する場合は、通常の労働契約に加えて「特定技能雇用契約書」といった専用の契約書が必要になります。契約内容には労働時間・賃金・社会保険の加入状況を明記し、認識の齟齬を防ぐためにも、外国人労働者本人が理解できる言語でも提示することが大切です。
雇用契約の段階で適正な労働条件を提示し、在留資格に沿った業務内容を定めることで、外国人従業員と企業の双方が安心できる雇用関係を築けます。
3. 在留資格の確認・申請
外国人雇用において、在留資格の確認と適切な手続き・申請がとくに重要です。ここを誤ると、採用が進められなくなる可能性があります。
採用する外国人材がすでに日本に在留している場合は「在留資格変更許可申請」や、「就労資格証明書交付申請」が必要となり、海外から呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
提出書類には、雇用契約書、労働条件通知書、業務内容を示す書類、在留カードの写し、卒業証明書などが含まれます。申請は出入国在留管理庁にて行い、審査には数週間から数カ月かかる場合もある点を把握しておきましょう。
必要書類を揃えて正しく申請を進めれば、不法就労のリスクを回避できるため、外国人労働者を安心して受け入れる体制が整います。
4. 入社手続き(保険・届出)
外国人労働者を受け入れる際は、社会保険や雇用保険の加入手続きと、外国人雇用状況届出を提出しましょう。
入社時には健康保険・厚生年金・労働保険などの加入手続きを進めるとともに、出入国在留管理庁へ「外国人雇用状況届出書」を提出します。これを怠ると、事業主は罰則を受ける可能性があるため注意してください。
労働条件通知書や雇用契約書も再度確認し、在留カードや在留資格認定証明書と内容が一致しているかをチェックしておくことも重要です。
入社手続きを適切に行えば、法令遵守を徹底できるため、外国人従業員が安心して就労を開始できる職場環境を整えられます。
5. 雇用後の支援・更新管理
外国人雇用では採用後も継続的な支援と在留期間更新の管理を行い、安定した雇用関係を築くことが大切です。
特定技能外国人や技能実習生を受け入れる企業は、登録支援機関と連携して外国人労働者の生活支援や、日本語学習の機会を提供する義務があります。
さらに、在留期限の管理を怠ると、不法就労や契約違反につながり、企業側も行政指導を受けるリスクがあるため適切に管理することが重要です。
雇用後の支援と更新管理を徹底すれば、外国人従業員の定着率向上につながり、企業の信頼性や人材活用力も高まります。
外国人材の採用前に必ず確認すべき「在留資格」と注意点
外国人採用を成功させるには、以下の在留資格の違いを理解し、業務内容と一致しているかを必ず確認しましょう。
| 在留資格の種類 | 概要・特徴 |
|---|---|
| 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務) | 専門性のある職種に限られており、単純労働は認められない |
| 特定技能外国人 | 人手不足の分野で働ける制度で、登録支援機関によるサポートが前提 |
| 技能実習 | 本来は国際貢献を目的としており、労働力確保を目的とした利用は違法 |
| 留学生 | 採用には在留資格変更許可申請が必要で、資格外活動許可だけではフルタイム就労不可 |
在留カードの確認や就労資格証明書の取得を怠ると、不法就労助長罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
在留資格の種類によって、従事できる労働・業務にも違いがあるため、必ず採用前に確認しておく必要があります。
外国人採用にかかる費用
外国人採用には、ビザ申請費用や人材紹介料、登録支援機関への委託料など複数のコストが発生するため、事前に総額を把握しておくことが重要です。
| 費用項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ビザ申請・在留資格認定証明書手数料 | 数千円〜数万円 | 出入国在留管理庁での申請手数料 |
| 行政書士への依頼費用 | 約10万円前後 | ビザ申請を専門家に依頼する場合の報酬 |
| 人材紹介会社の紹介料 | 年収の20〜30% | 採用時に一度支払うケースが多い |
| 登録支援機関への委託費用 | 月額数万円程度 | 特定技能外国人の受け入れで必要 |
| 社会保険・労働保険の企業負担 | 加入義務にともなう負担あり | 毎月発生する固定費用として考慮 |
出入国在留管理庁への申請手数料自体は数千円ですが、書類の不備や不許可になるリスクを避けるため、行政書士に依頼する企業もあります。
人材紹介会社への紹介料は高額に感じられるかもしれませんが、採用失敗のリスクを減らせるため、外国人採用に関するノウハウをもたない企業にとっては、費用対効果の高い手段です。とくに外国人材紹介会社のサービスには、在留資格の確認や面接時の通訳にも対応している場合が多く、活用すれば採用担当者の工数を大幅に削減できます。
外国人採用に必要な費用の内訳を理解して計画的に対応すれば、想定外の出費を防ぎつつ、外国人労働者との安定した雇用関係を築けるでしょう。
参考記事:【2025年最新版】外国人採用に強い人材紹介サービス8選|費用感と飲食・小売・施設向けおすすめの選び方を解説
外国人採用の流れを理解し、安定した雇用の実現を
外国人採用は、単なる人手不足の解消策ではなく、企業の成長戦略そのものです。
在留資格の適合確認や就労ビザの取得、雇用契約書の作成、登録支援機関との連携など、手続きを丁寧に進めれば安定した雇用関係を築けます。正しい知識が、信頼できる外国人雇用の第一歩です。
Bizcanでは、飲食店・施設の開業や経営に役立つさまざまな情報や設備・ツールについて情報を発信しています。
まずは、情報収集から着手してみるのもおすすめです。以下のリンク先より最新情報をご覧いただけます。