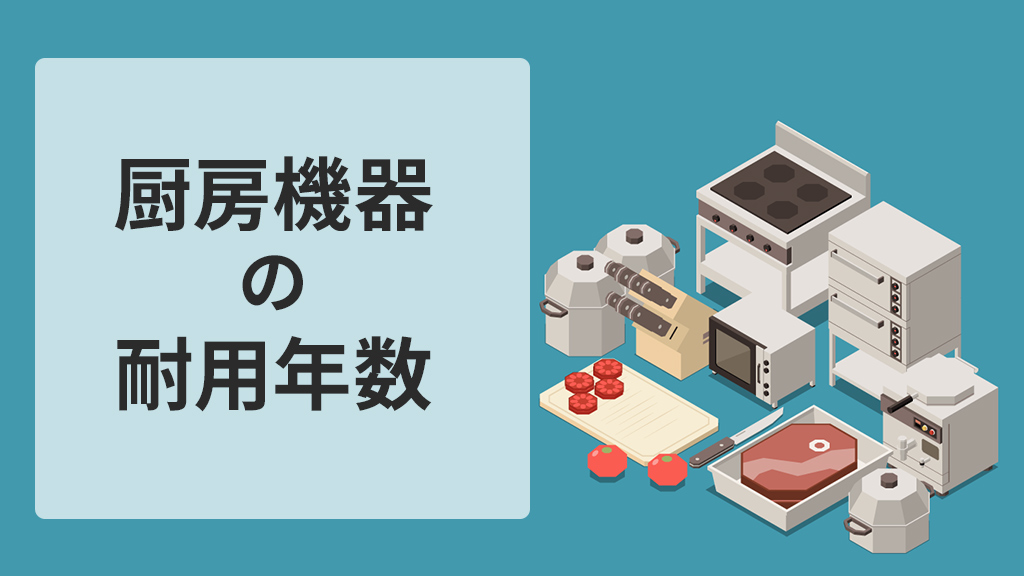「厨房機器の耐用年数は8年って本当?」
「中古の厨房機器を買ったら、耐用年数はどうなるの?」
といった疑問をお持ちの飲食店経営者の方も多いのではないでしょうか。
特に初めて店舗を持つ方や、設備更新を検討している方にとって、耐用年数や減価償却、会計処理の考え方はわかりにくいと感じるかもしれません。
しかし、これらの知識は資産管理や節税、経費計上の計画において非常に重要です。業務用厨房機器の法定耐用年数や減価償却の方法を理解することで、固定資産としての適切な扱いや、買い替え・リース・中古導入時の経費計上もスムーズになります。
本記事では、飲食店経営における業務用厨房機器の耐用年数の基本から、実務で使える減価償却の考え方、中古・リースの場合の対応までをわかりやすく解説します。
飲食店の業務用厨房機器の「耐用年数」とは?

飲食店の業務用機器に適用される「耐用年数」とは、減価償却資産(固定資産)として経費計上できる期間・年数、もしくは使用し続けられる期間のことです。
業務用の厨房機器には「何年使えるか」という目安があり、国(国税庁)によって、「法定耐用年数」として設備ごとに年数が定められています。飲食店で使う厨房機器の法定耐用年数は、2年~15年程度です。平均的な年数として「約8年」といわれています。
たとえば、業務用冷蔵庫の場合、法定耐用年数は6年となります。一方で、給排水設備の場合は15年に指定されているため、減価償却できる年数が異なる点に注意しなければなりません。
この年数は、設備が実際に壊れるまでの期間ではなく、経費計上(帳簿や税金の処理)のための目安です。厨房機器の場合、多くは6~8年とされています。飲食店の主な厨房設備・厨房機器の耐用年数表は以下のとおりです。
| 製品の種類 | 耐用年数 |
|---|---|
| 給排水・衛生設備/ガス設備 | 15年 |
| 電気冷蔵庫・電気洗濯機 | 6年 |
| 冷凍機付・冷蔵機付の陳列ケース | 6年 |
| 冷房用・暖房用機器 | 6年 |
| テーブル・椅子(接客業用) | 5年 |
| 食事・厨房用品(陶磁器製・ガラス等) | 2年 |
上記の表は代表的な例ですが、実際には機器の種類によって耐用年数に幅があるため、必ず国税庁の公式表をご確認ください。
2年~15年と年数にばらつきがありますが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によると、「飲食店業用設備」の業務用厨房機器は法定耐用年数が8年と定められています。
国税庁が定める耐用年数は表のようになっていますが、実際にはきちんとメンテナンスすれば10年以上使えることも珍しくありません。このように、「使える年数(物理的耐用年数)」と「会計処理を行う年数(法定耐用年数)」は異なる点が特徴です。
さらに、中古品を購入した場合は、以前使われていた年数を差し引いて「あと何年使えるか(見積耐用年数)」を新たに決め直すことになります。
厨房機器の耐用年数は、単に機器の寿命を示すものではなく、お金の計算や税金のルールに使われる大切な目安です。飲食店の経営者にとっては、設備の買い替えタイミングや節税にも関係するため、しっかり理解しておきましょう。
法定耐用年数 に基づく減価償却の考え方と計算方法

飲食店で使用される厨房機器は、購入した年に一括で費用計上するのではなく、「法定耐用年数」の基準に従い、複数年にわたって経費として処理する必要があります。基本的に、法定耐用年数による減価償却が必要になるのは、固定資産と呼ばれる取得に10万円以上かかる設備です。
たとえば、大型冷蔵庫やフライヤーのような10万円以上の機器は「固定資産」に分類され、法定耐用年数での減価償却計上が必要になります。国の定めによると、業務用厨房機器の法定耐用年数は一般的に8年とされており、機器取得にかかった金額を8年間に分割して経費計上するのがルールです。
このように、購入金額を法定耐用年数で割って経費計上することを「減価償却」といいます。
業務用厨房機器を減価償却して経費計上する方法には、毎年同じ金額ずつ分ける「定額法」と、初めの年に多く、後の年に少しずつ分ける「定率法」があります。
定額法は、取得金額を法定耐用年数で割って経費計上すれば良いため、経費計算が簡単に行える点が特徴です。
一方で、定率法は初年度の経費計上金額が高くなることから、取得した年度の節税効果を高くする形で経費計上できるメリットがあります。
減価償却とは?厨房機器が資産になる理由
減価償却とは、高額な機械や設備の費用を数年に分けて計上する方法のことです。厨房機器もこの対象になります。
厨房で使う機器は、一度買えば長く使えるものです。そのため、1年で費用にするのではなく、「何年か使えるモノ」として扱い、年ごとに少しずつ経費計上します。
たとえば20万円の業務用コンロを買ったら、法定耐用年数の8年に分けて毎年2万5,000円ずつ経費にする、という仕組みです。これが減価償却(定額法)になります。
厨房機器は日々使われて少しずつ古くなるため、その価値の減り方に合わせて費用にするという考え方が減価償却です。この方法は、減価償却が必要な固定資産における会計処理の基本になります。このほか、土地や建物などの不動産を取得した場合も、固定資産として法定耐用年数に則った減価償却処理が必要です。
減価償却費の計算例と勘定科目
厨房機器の減価償却費は、「いくらで買ったか」と「何年使えるか」によって計算し、勘定科目は「工具器具備品」として処理します。
たとえば60万円の冷蔵庫を買ったとします。国のルールでは耐用年数が6年と定められているため、毎年10万円ずつ経費計上します。これが「減価償却費」の定額法を用いた計上方法です。
厨房機器の減価償却イメージ(定額法の場合)について、60万円の業務用冷蔵庫を購入した場合(耐用年数:6年)に沿ってまとめた表が以下のとおりです。
| 年 | 減価償却費(年間) | 残りの帳簿価値(累計) |
|---|---|---|
| 1年目 | 10万円 | 50万円 |
| 2年目 | 10万円 | 40万円 |
| 3年目 | 10万円 | 30万円 |
| 4年目 | 10万円 | 20万円 |
| 5年目 | 10万円 | 10万円 |
| 6年目 | 10万円 | 0円(帳簿上の価値はゼロに) |
基本的に減価償却費は上記のように分割して処理します。
減価償却費は、会計上は「工具器具備品」という勘定科目で処理します。購入費用が10万円未満の設備の場合は、減価償却処理を行わず、勘定科目「消耗品費」として一括計上する方法が一般的です。
中古厨房機器やリース導入時の法定耐用年数と会計処理とは?
中古やリースで導入した厨房機器も、法定耐用年数やリース契約内容に基づいて減価償却を行い、適切な会計処理をする必要があります。それぞれのケースごとの法定耐用年数と会計処理について説明します。
中古の厨房機器の場合
中古品の場合、「あと何年使えるか」を決めるときは、国の決まりにしたがって、見積耐用年数を再設定しましょう。
たとえば、新品のときの法定耐用年数が8年でも、すでに2年使われた中古品なら、「残りは6年+α」として新しく年数を決め直します。(見積耐用年数)
一方、すでに8年以上使われているものは、最低でも2年として考えます。
このようにして、中古品を購入した場合は、見積耐用年数に分けて、購入費用を毎年経費計上することが可能です。
リースの厨房機器の場合
リース契約で厨房機器を使うときは、契約の内容によって処理方法が変わります。
最終的にその機器が自分のものになる契約(所有権移転リース)の場合は、 購入時と同じように減価償却することが可能です。勘定科目は「リース債務」と「支払利息」に分けて計上しましょう。
一方、リース期間が終わっても所有権が移らない契約(オペレーティングリース契約)の場合は、減価償却ではなくリース期間に応じて、リース料として経費処理します。
飲食店の業務用厨房機器の耐用年数を正しく理解し、賢い運用を
厨房機器の耐用年数を正しく理解し、減価償却や勘定科目などの会計処理に適切に対応することは、飲食店の資産管理や経営安定に直結します。特に、法定耐用年数8年を基にした償却計画は、長期的な設備投資の回収や税務戦略にも影響を与える重要な指標です。
また、中古の厨房機器やリース契約の導入に際しては、見積耐用年数や契約形態に応じた処理の違いに注意しましょう。厨房機器は「物理的耐用年数」と「会計上の法定耐用年数」が異なる場合も多いため、機器ごとの使用年数や劣化状況もあわせて管理することで、更新や修理のタイミングも見極めやすくなります。
たとえば、売上が伸びた年度に業務用厨房機器を購入し、定率法で減価償却を行って節税効果を高くするイメージです。
ただし、業務用厨房機器の取得には購入費用がかかるため、コストを抑えたい場合は中古やリース契約の利用も検討する必要があります。新品を購入する場合は、補助金・助成金制度をうまく活用して、コストを抑えるのも効果的です。
飲食店の設備投資や開業時の資金負担抑制に役立つ、補助金・助成金制度については以下の記事で解説していますので、ぜひ参照ください。