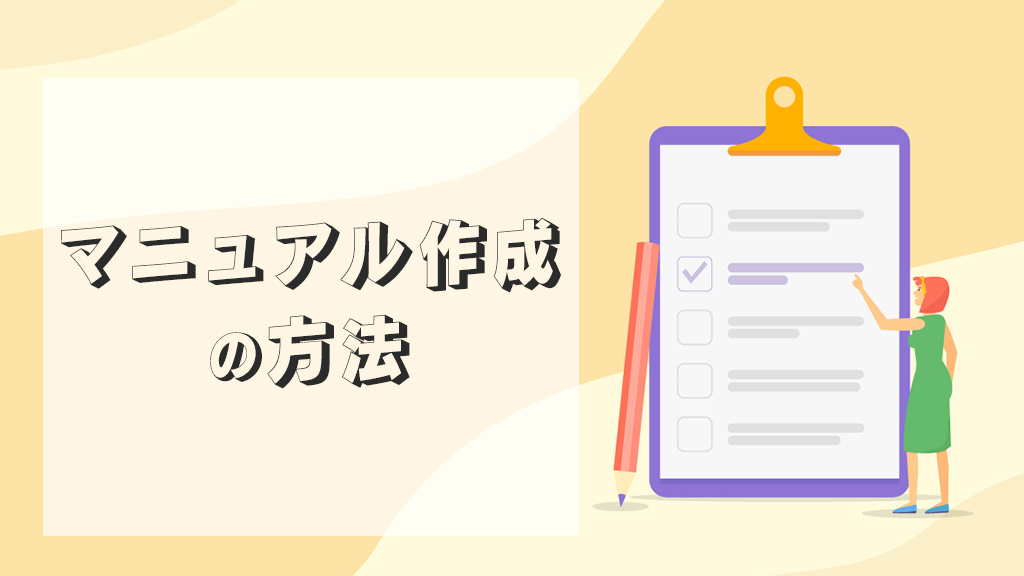業務マニュアルの作成を任されたものの、具体的にどういった方法で進めればよいか分からない、という担当者もいるでしょう。
たしかにマニュアル作成は日常的な業務ではないため、作成方法について知識がなければ戸惑うことも多いはず。そこで本記事では、マニュアル作成の方法や成功させるコツ、作成したマニュアルを有効活用する方法について解説していきます。
マニュアル作成の目的とは?
 そもそも何を目指してマニュアル作成をするか理解しておくことは重要です。
そもそも何を目指してマニュアル作成をするか理解しておくことは重要です。
本項では、マニュアル作成の目的を3つの観点から解説します。
業務品質の均一化
マニュアル作成の目的の一つは業務品質の均一化です。マニュアルが確立されていない業務の場合、業務を行う人によって業務品質には差が出てしまいます。特にサービス業の場合、業務品質に差が出てしまうと顧客満足度にも影響を及ぼしてしまうでしょう。
誰が業務を行っても一定の品質を確保できるよう、マニュアルを作成することで、業務品質を安定させることが可能になります。
業務効率化
マニュアルは業務効率の向上を目的として作成されることもあります。業務効率は従業員のスキル・知識、リソースなど、さまざまな要因によって左右されます。また、業務フローが確立されていない状況では業務効率が人に依存してしまうことも考えられるでしょう。
効率的に業務を進める手順書としてマニュアルを作成することで、全体の業務効率化に貢献することが可能です。
ナレッジの共有
マニュアル作成の目的の一つに、ナレッジの共有が挙げられます。日々働く中で、従業員個人個人にはさまざまなナレッジが蓄積されていきます。しかしながらナレッジを共有する機会は中々ない、という企業も多いでしょう。
マニュアル作成の際に個人の持っているナレッジを落とし込んでいくことで、組織全体でナレッジを共有することが可能です。
業務を効率化したい、業務の品質を均一化したい、社内のナレッジを共有したい場合に、
マニュアルを作成することになります。
マニュアルの作成方法とは?
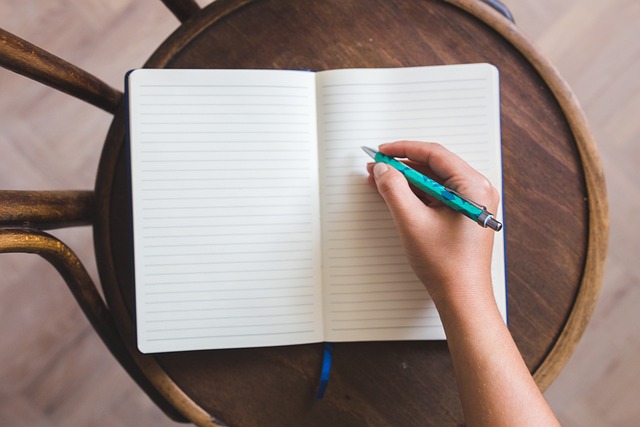 続いて、マニュアル作成に必要な具体的な手順について解説します。
続いて、マニュアル作成に必要な具体的な手順について解説します。
作成する目的を決める
マニュアルを何故作成するのかという目的の設定は重要です。業務品質の均一化や改善、効率化や俗人化の回避など、作成する目的はさまざまです。
マニュアル作成の目的を第一段階で設定しておくことで、マニュアルに必要な要素が明確になります。たとえば業務効率化やナレッジの共有が目的となる場合、業務手順はもちろん、業務を効率化するTipsなどを盛り込むことでより目的に近づくはずです。
マニュアルに必要な内容を明確化するためにも、目的の設定は必ず行いましょう。
スケジュール調整をする
次にマニュアル作成のスケジュール調整を行いましょう。いつごろまでにマニュアルの運用を開始すべきなのかイメージしたうえで、逆算してマニュアル作成のスケジュール調整をしていきます。
また、マニュアルの作成者にも日々のコア業務がある場合、作成者のリソースを圧迫しすぎないよう、無理のないスケジュールを策定していくことも重要です。
マニュアルの構成を作成する
スケジュールの調整が完了したら、マニュアルの構成を作成していきましょう。目次や見出し、ページ構成といった枠組みを作成したうえで、具体的な内容の作成に入っていきましょう。
構成の作成においては文書作成ツールなどに内容をまず作成していき、画像や
動画といった各種素材も揃えつつ、内容の制作をする準備を進めていきましょう。
フォーマットに落とし込む
構成の作成が完了したら、フォーマットに内容を落とし込んでいきましょう。自社で使用しているマニュアルのフォーマットがある場合はそれを利用しても問題ありませんが、フォーマットがない場合はマニュアル作成ツールを利用してフォーマットを使うのがおすすめです。
また、一からフォーマットを作成する、フォーマットなしで制作を進める場合は注意しましょう。基本的には、作られたフォーマットに内容を当てはめていく方が無難といえるでしょう。
4つのステップに分けてマニュアル作成を進めていきましょう。
マニュアル作成を成功させる方法とは?
 本項では、マニュアル作成を成功に導く上でのポイントについて解説します。
本項では、マニュアル作成を成功に導く上でのポイントについて解説します。
業務の全体像を理解できる構成を作る
マニュアルの構成を作る際は、業務の全体像を読み手が理解できるように作成しましょう。たとえば「企画書の作成方法」に関してマニュアルを作る場合、企画書を作成する際の始まりと終わりを順序だててマニュアルを作成することが重要です。
マニュアルの順序がちぐはぐになっている、途中で異なる業務にトピックが飛んでしまうといったことがあると、読み手は業務の全体像を把握しづらくなってしまうでしょう。こうした事態を避けるためにも、マニュアルを構成する時点で業務の全体像を順序だてて作成することが重要といえます。
無理のないスケジュールを引く
マニュアル作成をする際は、無理のないスケジューリングを行いましょう。余裕のないスケジュールでマニュアル作成を始めてしまうと作成者の業務負担が増してしまい、マニュアル自体の質も低下してしまう恐れがあります。
期日を決めてマニュアル作成を進めるのは良いことですが、作成者にとって無理のないスケジュールで作成を行うのが無難です。
適度に図解を活用する
マニュアル作成では文字だけですべてを説明するのではなく、適度に図解や画像、動画など、視覚的に理解できる要素を活用しましょう。業務によっては文章の説明だけでは読み手がイメージしづらく、理解が難しいものもあるでしょう。特に手作業を要する業務の場合、実際に業務をしている画像などを添えた方が理解がしやすくなります。
文章だけで説明するのではなく、適度に視覚的な要素を盛り込み、補足として説明文を記載することを意識するのがおすすめです。
本項で解説したポイントをおさえて、マニュアル作成を成功させましょう。
作成したマニュアルを無駄にしない3つのポイントとは?
せっかくマニュアルを作ったとしても、有効活用できなければ意味がありません。本項では、作成したマニュアルを有効活用するためのポイントを解説します。
使い方について社内で共有する
マニュアルの運用方法については社内で必ず共有するようにしましょう。どのような内容のマニュアルになっており、どういった場面で活用すべきなのか、社内で共通認識を持てるよう、情報共有しておくことが重要です。
マニュアルが完成したことを周知するだけでなく、どのように使えばよいか、一度ミーティングの時間を使って解説しておくことで、認識の齟齬を予防することができます。
改善点は常にブラッシュアップをかける
マニュアルを完成させ、運用を開始した後も、改善点に関しては常にブラッシュアップをかけるようにしましょう。マニュアルを使い始めてから「分かりづらい」「使いづらい」という部分が見えてくることもあるはずです。
改善点をそのままにするのではなく、実際にマニュアルを使用している従業員にヒアリングをしつつ、見つかった改善点については定期的に修正をかけることが重要です。
クラウド上でマニュアルの管理を行う
データでマニュアルを管理する場合、クラウド上でマニュアル管理を行うことをおすすめします。クラウド上であれば編集権限を設定することができるうえ、手を加える際も複数人で作業することができます。また、誰が最終更新をしたのか明確に出来るのも便利です。
特にマニュアルの活用方法を従業員に周知し、共有しておくことは重要です。
まとめ
本記事では、マニュアル作成の方法や成功させるコツ、作成したマニュアルを有効活用する方法について解説しました。しっかりと手順を踏んでマニュアル作成をすることで、分かりやすいマニュアルに仕上げることができます。また、マニュアルをどのように活用すべきか事前に決めておくことも重要です。本記事の内容を参考に、マニュアル作成に役立ててみてください。