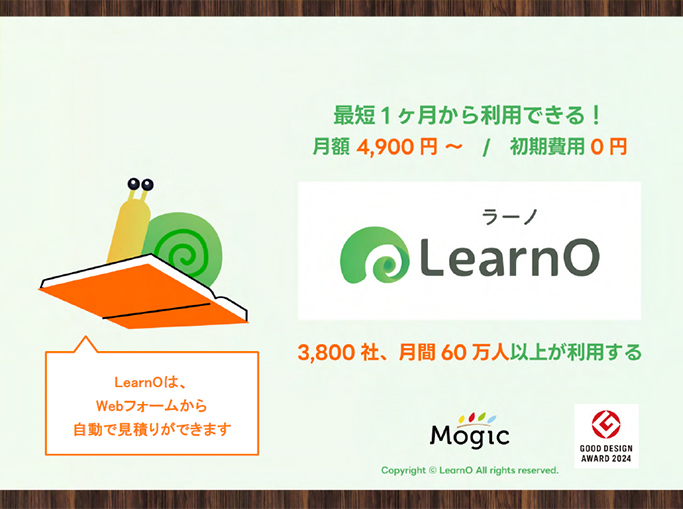企業の研修や自己啓発など、社員育成に役立つツールの1つがeラーニングシステムです。
対面での研修とは異なり、指導する社員の業務負担軽減につながる特徴があります。しかし、eラーニングシステムを導入することに対して、費用の負担が発生する点や自社に合うシステムが導入できるか不安に思っている方もいるでしょう。
本記事では、eラーニングシステムとはなにか、導入するメリット・デメリットに加え、最適なシステムの選び方について解説します。また、費用を抑えるポイントについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
eラーニングシステムとは

eラーニングシステムとは、インターネットを介して研修や自己啓発を行う学習形態のことです。研修を先輩社員が行わずに済むため、指導の効率化が図れます。
また、誰がいつどのようなカリキュラムを学習したのかを管理したり、複数のカリキュラムを通じてスキルアップや知識の向上につなげたりするのも活用方法の1つです。
eラーニングシステムは、社内で構築する方法のほかに、基本的なカリキュラムがパッケージ化されているものもあるので、状況に応じて活用方法を検討すると良いでしょう。
eラーニングシステムを導入するメリット
企業でeラーニングシステムを導入するメリットは、以下の3点です。
- 教育の質が統一される
- 学習の進捗状況を一元管理できる
- 受講時間や場所に縛られない
それぞれ具体的にどのような効果があるのか、詳しく解説します。
教育の質が統一される
eラーニングシステムを導入すると、教育の質が統一されて社員の差を均一に保てるメリットがあります。
同一のカリキュラムで、多数の社員が学習できるためです。大規模な会議室などで研修を行った場合、指導者やモニターから遠い位置にいる社員は聞き取りにくい状況になります。
eラーニングシステムであれば、同一の環境で学習が進められるため、このような座席配置の影響が発生することもありません。
また、指導者によって教え方が異なるなどの差もなくなり、指導力の属人化を防ぎながら、同一水準の知識やスキルを身に付けられます。
学習の進捗状況を一元管理できる
学習の進捗状況を一元管理でき、学習管理システムとして活用できるのも、eラーニングシステムを導入するメリットの1つです。
システム上で、管理者が受講者や学習者の情報を確認できるため、学習状況の差や遅れなどがないかをいつでも把握できます。
個別に管理する必要がなくなる上に、受講者のつまづいているポイントなども明確になり、指導に反映しやすいのも特徴です。
状況に応じて個別で丁寧にフィードバックや指導を行うなど、より丁寧なフォローにもつながるでしょう。
受講時間や場所に縛られない
eラーニングシステムは、受講時間や場所に縛られずに学習が進められるメリットもあります。
会議室などを利用して講義や研修を行う場合、指定された時間・場所で受講しなければならず、スケジュール調整の負担が生じる要因です。
一方で、eラーニングシステムであれば、インターネット環境さえあればいつでもどこでも学習教材が利用できるため、社員の受講向けたスケジュール調整の負担も軽減できるでしょう。
また、近年では「マイクロラーニング」と呼ばれる5~15分ほどの短時間で、自主学習ができるカリキュラムを導入する企業も増加傾向にあります。隙間時間を有効活用できるため、このような短時間学習の活用もおすすめです。
eラーニングシステムを導入するデメリット
eラーニングシステムを導入するデメリットは、以下の3点です。
- 実技やスキルの習得には適していない
- インターネット環境が必要
- モチベーションを維持することが難しい
それぞれどのような影響があるのか、eラーニングシステムを導入する前に把握しておきたい注意事項を踏まえて、詳しく解説します。
実技やスキルの習得には適していない
実技やスキルを習得するための学習に適していないのは、eラーニングシステムを導入するデメリットの1つです。
実務経験が必要になる業務に関しては、実際に先輩社員の作業や業務の進め方を目で見て覚える必要があります。
動画を用いて学習する方法もありますが、知識や経験が必要になるような実技の場合は、直接指導しなければ伝わらないこともあるでしょう。
eラーニングシステムは、個別学習に適している反面、このような実技・実践スキルが求められる業務の学習には適していない点に注意が必要です。
インターネット環境が必要
eラーニングシステムを利用する際、インターネット環境が必要になるのもデメリットの1つです。
インターネット環境が整っていない場所では、学習できないため、結局従来通りの人から人への指導が必要になります。
eラーニングシステムを導入するのと同時に、インターネット環境を整えなければならない点に注意が必要です。
モチベーションを維持することが難しい
学習に対するモチベーションを維持することが難しいのも、eラーニングシステムを導入するデメリットの1つです。
eラーニングシステムでの学習は、個人がそれぞれに行うため、独学に近い環境で学習を進めなければなりません。
会議室などで行う集合研修や、先輩社員から直接指導を受けるのと比べて、人の目がない分、モチベーションの維持が難しくなります。
定期的に面談やフィードバックを行うなど、モチベーションを維持するために伴走支援を行うことが大切です。
eラーニングシステムは意味がないのか?
前項ではeラーニングシステムのデメリットを解説しましたが、結論から言えば、企業研修や社員教育でのeラーニング導入は「意味がない」のではなく、正しい運用と活用方法によって、大きな教育効果を発揮します。
「eラーニング研修は学習効果が薄い」「結局、学習定着しない」と感じている方もいるかもしれません。しかし、こうした声の多くは、学習者の学習意欲や管理体制が整っていない場合に発生するものです。
eラーニングが「意味がない」と誤解される背景には、以下のような課題があります。
- 教材コンテンツが受講者に合っていない
- 学習進捗の「見える化」ができていない
- 動画教材を“流し見”するだけで終わっている
こうした状況では、たしかに「スキルアップ」や「理解度の向上」にはつながりにくいでしょう。
しかし、近年のeラーニングシステムには、進捗管理機能・テスト機能・スキル別eラーニング教材の配信機能などが備わっており、受講者ごとの理解度に応じたカスタマイズ学習が可能です。
たとえば、「新入社員研修」では基本知識を一元管理しながら、「管理職研修」では階層別に応じたマネジメントコンテンツを配信するなど、学習目的に応じた運用ができます。
さらに、「動画教材×テスト」「受講履歴×フィードバック」の組み合わせにより、学習者のモチベーションを維持しやすい設計も可能です。
適切な「管理機能による受講管理」や「学習コンテンツの最適化」を行えば、eラーニング学習は自社教育での人材育成の軸として十分に機能します。
自社に最適なeラーニングシステムの選び方

さまざまな機能や特徴があるeラーニングシステムの中で、自社に最適なものを選ぶにはどのような基準で比較すれば良いのでしょうか。
ここからは、自社に最適なeラーニングシステムを選ぶための比較基準や、導入するシステムを決定するポイントについて解説します。
eラーニングシステムの種類で選ぶ
自社に最適なeラーニングシステムを選ぶには、まずeラーニングシステムの種類を絞り込むことが大切です。
クラウド上で学習ができるSaaS型や、ある程度のカリキュラムが設計されているパッケージ型、オンライン上にソースコードが開示されているオープンソース型など、さまざまな種類の中から選択できます。
まずは種類を絞り込んだ上で、対応しているeラーニングシステムのサービスを比較検討すると良いでしょう。
導入・運用にかかる費用で選ぶ
導入するeラーニングシステムを選ぶ際、導入・運用にかかる費用での比較も行いましょう。
どれだけ優れたeラーニングシステムであっても、導入・運用にかかる費用が予算を上回っていると本末転倒です。
eラーニングシステムそのものの機能や、カリキュラムの充実度などで比較することも大切ですが、妥当な費用か否かを検討する必要があります。
機能で比較する
自社に最適なeラーニングシステムを導入するのであれば、eラーニングシステムの機能で比較検討することも重要です。
教材やカリキュラムの管理機能だけでなく、受講後のテスト・レポート作成機能や、受講者全員の受講・進捗状況が確認できる機能は備わっているかなど、必要な機能の有無をチェックしておきましょう。
ただし、機能が豊富なものほど導入・運用にかかるコストが高くなるため、費用とのバランスを見極める必要があります。
eラーニングシステムの導入費用を抑えるポイント

eラーニングシステムは、サービスを提供している事業者によって価格設定に大きな違いがあります。また、オープンソース型のように無料公開されているものがある反面、カスタマイズするためのエンジニア人材などが必要になる点に注意しましょう。
ここでは、eラーニングシステムの導入にかかる費用を抑えるポイントについて、詳しく解説します。
オープンソース型のeラーニングシステムを導入する
eラーニングシステムの導入費用を抑える選択肢として、オープンソース型のeラーニングシステムを導入する方法があります。
オープンソース型であれば、インターネット上にソースコードが無料で公開されていることが多いためです。自社の状況に合わせて任意のカスタマイズが行えるなど、オリジナルのeラーニングを作成したい企業にも適しています。
ただし、独自のカリキュラムを作成するためのコード知識などが必要になるため、専門知識をもつ人材が社内にいなければ難しい点に注意しましょう。
SaaS型を導入して保守管理コストを下げる
SaaS型eラーニングシステムを導入して、保守管理コストを下げるのもおすすめです。
SaaS型は、クラウド上で利用できる学習ツールのため、サービスを提供している事業者が保守管理やアップデートなどを行っています。
そのため、自社内にeラーニングシステムを構築せずに済むことから、保守管理を行う人材がいない企業やコストカットを図りたい場合に最適です。
初期費用や月額料金はある程度発生しますが、エンジニア人材を採用・育成する負担が軽減できるメリットもあります。
eラーニングシステムの受講方法
eラーニングシステムの受講方法は、専用の「学習管理システム(LMS)」にログインし、配信された「教材コンテンツ」や「動画教材」を活用しながら、自分のペースで学習を進めるのが基本です。
具体的に、以下のようなステップで学習を進めます。
① ログイン
企業や教育機関が提供するeラーニングシステムに、受講者IDとパスワードでアクセスします。
② 学習内容の選択
eラーニングシステム内には、あらかじめ設定された「学習コンテンツ」「スキル別eラーニング教材」「オンライン研修動画」などが用意されています。必要な講座を選択し、任意の順番で学習を進めることが可能です。
③ 学習の進捗と評価の記録
eラーニングシステムには、以下のような便利な機能が搭載されています。
進捗管理機能:どこまで学んだかを可視化
テスト機能:理解度を確認
学習履歴の保存:自動記録で復習にも役立つ
上記の機能により、受講者は自分の「学習状況」を確認でき、教育担当者や管理者は「全受講者の進捗や達成率」を一括で把握できます。
④ デバイス対応でスキマ学習
多くのeラーニングシステムは、スマートフォン・タブレットといったスマートデバイスに対応しています。
通勤中や休憩時間などの隙間時間を有効活用でき、時間と場所に縛られず学習を進められるのがメリットです。
⑤ 「動画教材」で記憶定着も効率化
視覚・聴覚からの情報入力により、記憶への定着率アップにも役立ちます。文字だけの教材と比べて、理解しやすく、実践的な学びにもつながるでしょう。
このように、eラーニングシステムは時間や場所にとらわれない柔軟な学習スタイルを提供してくれます。学習意欲を高めながら、着実なスキルアップが可能な点が、多くの企業に選ばれている理由の1つです。
まとめ
eラーニングシステムは、指導効率の向上などに役立つツールの1つです。しかし、導入する際に自社の状況に合うものを選ばなければ、費用が膨れ上がったり、かえって指導効率が下がったりする可能性があります。
まずは、自社のどのような指導や研修などの学習コンテンツをカリキュラム化したいのかを明確にした上で、実現可能なeラーニングシステムを選ぶことが大切です。