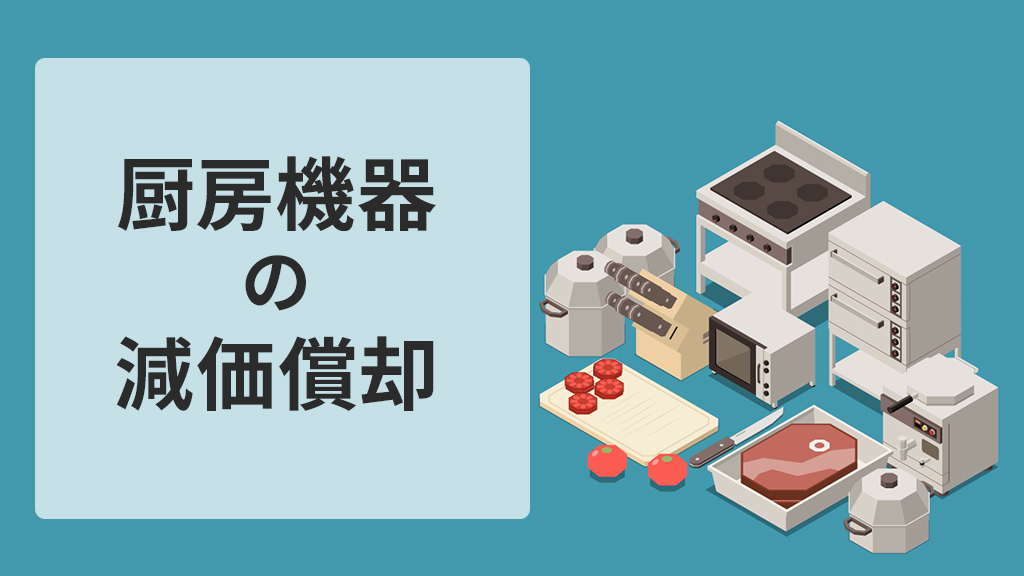記事タイトル
飲食店の開業や経営には、冷蔵庫や製氷機、ガス機器といった厨房機器を含む「減価償却資産」の購入が避けて通れません。中でも業務用厨房機器は高額な設備投資となるため、その費用をどのように会計処理するかが、経営の損益に大きく影響します。特に厨房機器の法定耐用年数が「8年」と定められていることを知らずに経費処理を進めると、税務上の不利益を被りかねません。
そこで本記事では、「厨房機器の減価償却とは何か?」という基本から、法定耐用年数の根拠、定額法・定率法による計算方法、中古品やリース契約の場合の扱い、さらに節税につながる経費計上のポイントまで、実践的な内容を網羅的に解説します。
そもそも「減価償却」とは?厨房機器が対象になる理由

減価償却とは、10万円以上の固定資産を購入した際、その費用を複数年に分けて経費として計上する会計処理のことです。
たとえば、厨房用機器や厨房器具、調理機器といった業務用厨房設備は耐久性が高く、複数年にわたって使用されるため、税法上は「減価償却資産」に分類されます。
飲食店で「家庭用の冷蔵庫」ではなく「業務用厨房機器」を購入した場合、減価償却を行うことで税務上の所得を圧縮でき、結果として節税につながります。
厨房機器はその高額性と耐久性から、単なる備品ではなく飲食店の「資産」として戦略的に管理すべきでしょう。減価償却を正しく理解すれば、税務上の負担を軽減しつつ、設備投資のリスクをコントロールできます。
厨房機器の法定耐用年数は8年!その根拠は?
業務用厨房機器の法定耐用年数は原則8年とされており、これは国税庁が定めた「減価償却資産の耐用年数表」に基づいています。
「法定耐用年数」とは、国税庁が定めている減価償却の計算に使われる基準年数です。
一方で「耐用年数」という言葉には、“実際に機器を使用できる期間(物理的・経済的寿命)”という意味もあり、混同しやすいため注意しましょう。
「法定耐用年数8年」という数字は、機器の平均的な稼働環境を前提に設定された年数です。油や熱、湿気など過酷な厨房環境を考慮すると、実際の使用可能年数とは乖離するケースも多くあります。
実際の厨房では10年以上使われる機器も珍しくなく、「まだ使えるのに減価償却は終わっている」という現象も起こります。逆に、厨房の使用頻度やメンテナンス状態、故障状況によっては、8年未満で寿命を迎えることもあるため、耐久性と税務上の処理は切り分けて考えるべきです。
法定耐用年数8年という基準は、あくまで「税務上の償却ルール」に過ぎません。店舗経営者はこれを鵜呑みにせず、実際の使用状況や買い替え判断と切り分けて考える必要があります。
業務用厨房機器の耐用年数については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらを参考にしてください。
参考記事:【飲食店経営者必見】業務用厨房機器の耐用年数は8年?減価償却・中古の場合を解説
【定額法】厨房機器の減価償却の計算方法

定額法は、厨房機器の固定資産を毎年一定額で減価償却する方法です。定額法によって減価償却する場合、会計処理がシンプルになり、節税効果も均等に得られます。
厨房機器を導入した場合、多くの中小企業や個人事業主では「定額法」で減価償却を行います。定額法は毎年の会計処理が一定で読みやすく、経営管理や資金繰りの予測にも活用しやすい点がメリットです。初期費用が大きくなりやすい厨房機器こそ、定額法の減価償却によってキャッシュフローを安定させる効果が期待されます。
定額法では、資産の取得価額から残存価額(資産の最後に残ると見なされる価値のこと。通常5%)を差し引いた額を法定耐用年数で割り、毎年同じ「減価償却費」を計上するのが特徴です。
たとえば、100万円の業務用冷蔵庫を新品で購入した場合、耐用年数は8年・残存価額は5万円(=100万円の5%5%)なので、償却額は以下のように計算されます。
- 償却可能額:100万円 – 5万円 = 95万円
- 年間償却費:95万円 ÷ 8年 = 11万8,750円
この11万8,750円を毎年経費として計上できるため、計画的な節税が実現します。
定額法は、業務用厨房機器の減価償却を安定的に行えるベーシックかつ実用的な手法です。毎年一定額を経費として計上できるため、会計・税務処理のわかりやすさと節税のバランスが取れています。
【定率法】厨房機器の減価償却の計算方法
定率法とは、毎年の未償却残高(=取得価額からこれまでの償却額を差し引いた金額)に一定の償却率(定率)を掛けて減価償却を行う方法です。
これにより、初年度は償却額が大きくなり、年を追うごとに償却額が減少するという特徴があります。そのため、定率法は初期の経費圧縮に適しているのが特徴です。
たとえば、100万円の業務用冷蔵庫を新品で購入し、耐用年数は8年・定率法償却率0.25の場合、減価償却費は以下のように計算されます。
- 初年度償却額:100万円 × 0.25 = 25万円
2年目以降は、前年までの償却分を差し引いた残高に同じ償却率を掛けて計算します。
定率法は、飲食店の開業初期に大きな償却を行いたい店舗経営者にとっての強力な節税手段です。
中古厨房機器やリース契約の場合の減価償却はどうする?
中古厨房機器は、使用可能期間に応じた「見積耐用年数」で減価償却を行います。
リース契約では「契約形態」に応じて償却方法が異なるので、個別に確認しましょう。それぞれの減価償却について表で説明します。
| 取得形態 | 減価償却の要否 | 耐用年数の決め方 | 会計処理方法 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 中古厨房機器 | 必要 | 見積耐用年数(※1) | 固定資産として計上、定額法or定率法 | 実際の使用可能期間に応じた年数で算出可能 |
| 所有権移転リース契約 (最終的にその機器が自分のものになる契約) |
必要 | 原則、法定耐用年数(または契約内容による) | リース資産として資産計上、減価償却実施 | 実質購入扱い、資産として管理が必要 |
| オペレーティングリース (リース期間が終わっても所有権が移らない契約) |
不要 | ― | 月額リース料を経費計上(リース料処理) | 借用契約扱い、資産にも減価償却にも含めない |
※1:見積耐用年数 = 「法定耐用年数-経過年数」+(経過年数 × 20%)※1年未満切り捨て、2年未満なら2年とする
このように、中古機器やリース契約では取得形態によって減価償却方法が大きく異なるため、資産計上・償却年数・経費計上のルールを正確に理解することが重要です。
厨房機器の減価償却を行うメリット・デメリット
厨房機器の減価償却には節税や資金繰りの面でメリットがある一方で、処理の手間や管理面でのデメリットも存在します。
- 厨房機器の減価償却を行うメリット
- 厨房機器の減価償却を行うデメリット
ここでは、厨房機器の減価償却を行う際に知っておきたい、代表的なメリットとデメリットについて解説します。
厨房機器の減価償却を行うメリット
厨房機器の減価償却を行うことで、厨房機器の費用を複数年に分散でき、毎年の利益を圧縮して節税につなげられるのがメリットです。
厨房機器のような高額資産は、購入年度に一括経費化できませんが、減価償却により毎年一定額を経費にできます。これにより、税負担を平準化し、資金繰りの安定に貢献します。また、節税効果も見込めるため、経営戦略上有利です。
減価償却は税務上のメリットがあるだけでなく、長期的な設備投資管理にも役立つ会計処理です。
厨房機器の減価償却を行うデメリット
減価償却には節税効果がある一方で、会計処理が煩雑になり、経理担当者の負担が増す点がデメリットです。
減価償却では法定耐用年数や償却率、償却方法(定額法・定率法)の選定など専門知識が求められ、特に中古やリースの場合は判断が難しくなります。また、資産台帳の管理や償却漏れ防止の体制も必要です。
減価償却には注意すべき点も多いため、税理士や会計ソフトの活用で処理の正確性を担保しましょう。
減価償却を活かした飲食店の節税・経費計上のポイント
厨房機器の減価償却を活用して、取得価額・法定耐用年数・償却率を正しく管理することで、所得圧縮による継続的な節税と、税負担の均等化が可能です。
減価償却費を計上して所得を圧縮
厨房機器などの固定資産を取得価額に基づき耐用年数で償却すると、毎年安定した経費を計上できます。
その結果、課税対象所得を抑えられるため、税額の軽減につながります。
厨房機器の導入時は「取得価額」「法定耐用年数」「償却率」を必ず確認
上記3点は、減価償却費の計算に不可欠です。法定耐用年数は国税庁が定める表から参照し、償却率は資産分類ごとに決まります。
正確な数字がなければ、節税効果が損なわれかねないため、必ずチェックしましょう。
厨房機器の定期的な買い替え計画で、費用分散と税負担の均等化を
厨房機器を耐用年数終了時に買い替えることで、毎年の償却費が均等化されます。さらに、固定資産税の一種である「償却資産税」では、資産合計評価額が150万円以下で非課税となるルールがあるのが特徴です。そのため、厨房機器の導入時期と資産総額を調整することで、税負担を抑制できます。
取得費用の分散、節税、税負担の均等化を実現するには、厨房機器の取得価額・耐用年数・償却率を適切に把握し、計画的に減価償却を進めるのがポイントです。
業務用厨房機器の買い替え・導入タイミングはいつが得?
業務用厨房機器の買い替え・導入は、耐用年数の終了タイミングや決算期直前に実施することで、減価償却による節税効果や償却資産税の負担軽減につながります。
法定耐用年数が8年と定められている厨房機器は、多くの場合それ以上の年数使えます。しかし、故障や性能劣化のリスクを考慮すると、耐用年数終了時に買い替えるのが理想です。
また、決算期前の導入であればその年度から減価償却費を計上できるため、早期に節税効果を得られます。
さらに、償却資産税の非課税枠(150万円以下)を意識して導入計画を調整すれば、税負担も抑えられるためお得です。補助金制度を活用すれば、初期費用の削減と経費計上の両立もできます。
参考記事:【2025年最新】厨房機器の導入で使える助成金・補助金5選|中小飲食店・個人事業主向け申請ガイド
厨房機器の買い替えや導入は、「耐用年数」「決算タイミング」「償却資産税」などを総合的に考慮して進めることで、経営効率と節税効果を高められます。導入前には税理士や業者と相談しながら、長期的な費用対効果まで見据えて計画を立てましょう。
厨房機器の減価償却は飲食店の経営判断の要
厨房機器の減価償却は、単なる会計処理ではなく、飲食店の経営戦略に直結する重要なテーマです。法定耐用年数8年という基準を正しく理解し、取得価額や償却率、残存価額をもとに毎年の償却費を的確に算出することで、安定した経営と節税効果が期待できます。
特に、中古機器やリース契約の場合は個別の会計処理が求められます。ミスを防ぐためにも、税理士や専門業者との連携が重要です。厨房機器の導入時期や資産の合計額によっては償却資産税の負担も軽減できるため、厨房機器の更新は戦略的に行いましょう。