小さな居酒屋を開業したい、飲食店を開業したいが具体的にどのような資格が必要なのかがわからない、など、居酒屋の開業に向けて資格取得を検討している方もいるでしょう。
しかし、資格を取得するのにどれくらいの時間を要するのか、いつから準備を進めれば良いのかなど、初めて開業する方にとってわからないことが山積しているのも現状です。
今回は、そのような方に向けて、居酒屋開業時に必要な資格や取得にかかる時間の目安、取得しておくと便利な資格について詳しく解説します。
また、居酒屋の開業時に必要な届出・許認可、必要資金の目安についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
居酒屋の開業に必須の資格・許認可
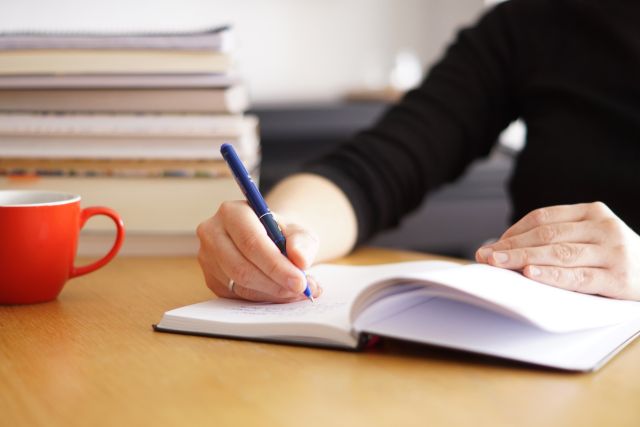
居酒屋の開業に必須の資格・許認可は、以下のとおりです。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
- 飲食店営業許可
- 酒類販売業免許
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
それぞれ、資格・許認可の概要と、取得にかかる時間の目安や届出のタイミングについて解説します。
食品衛生責任者
食品衛生責任者の資格は、居酒屋のみならず飲食店を開業する際に必須の資格です。店舗をもたない、キッチンカー・フードトラックを開業する場合でも必要になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必須の理由 | 飲食店営業許可の取得条件として、各店舗に1名以上の食品衛生責任者を配置することが食品衛生法で義務付けられているため。食中毒の予防や衛生管理体制の確立を担う。 |
| 取得方法 | 各自治体(保健所)が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、修了証を取得する。 |
| 取得費用 | 目安10,000円前後(自治体により約8,000〜12,000円程度の幅あり)。 |
| 取得要件 | 特別な学歴や実務経験は不要。原則だれでも受講可能(自治体により年齢要件等が設けられる場合あり)。食品関連の国家資格保持者は申請のみで取得できるケースがある。 |
| 取得にかかる時間の目安 | 通常は1日(約6〜7時間)で、修了試験は原則なし。調理師・栄養士等の有資格者は講習免除となる場合がある。 |
基本的に1日~2日で取得できる資格ですが、食品衛生責任者資格を取得していないと飲食店開業許可の許認可申請ができません。
そのため、飲食店開業許可を申請する前の段階で、早めに取得しておく必要があります。
防火管理者
防火管理者の資格は、消防法によって定められた火災予防・避難訓練や誘導のための責任者資格です。
飲食店のみならず、一定規模以上の防火対象物には防火管理者の選任が義務付けられており、ホテルや施設、オフィスビルなど多種多様な建築物が対象となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必須の理由 | 消防法により、収容人員30人以上の飲食店や一定規模以上の防火対象物には、防火管理者の選任が義務付けられているため。火災予防や避難訓練計画の作成など、防火安全管理の責任者となる。 |
| 取得方法 | 消防署または消防関連機関が実施する「防火管理者講習」を受講し、修了証を取得する。甲種(全用途対応、2日間)または乙種(収容人員300人未満、1日間)があり、用途や規模により選択。 |
| 取得費用 | 甲種・乙種ともにおおむね6,000〜8,000円程度(自治体や実施機関によって異なる)。 |
| 取得要件 | 18歳以上で、施設の管理権限を有する者またはこれに準ずる立場の者。学歴や専門資格は不要だが、甲種を取得する場合は一部条件により受講資格の確認が必要なことがある。 |
| 取得にかかる時間の目安 | 講習受講は甲種が2日間、乙種が1日間。申込から受講までの期間は開催スケジュールによるが、1週間〜1か月程度かかることが多い。 |
建築物の収容人数・規模によって必要な資格が異なるため、開業する居酒屋の規模に応じた資格を取得しましょう。
飲食店営業許可
飲食店営業許可は、居酒屋だけでなく幅広い業態の飲食店を開業する際に必須となる許認可です。出店する居酒屋の店舗がある地域を管轄している保健所で、申請する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必須の理由 | 食品衛生法に基づき、飲食物を調理・提供する営業を行う場合には、保健所から「飲食店営業許可」を取得することが義務付けられているため。衛生基準を満たした施設であることを確認するための制度。 |
| 取得方法 | 営業施設の図面や必要書類を準備し、営業開始予定地を管轄する保健所へ申請。施設検査を受け、基準に適合すれば許可証が交付される。申請時には食品衛生責任者の設置が前提。 |
| 取得費用 | 申請手数料は自治体によって異なるが、概ね15,000〜20,000円程度。施設改装や設備導入が必要な場合は別途費用が発生。 |
| 取得要件 | 食品衛生法に定める施設基準を満たすこと(給排水・調理設備・換気・照明・害虫防除など)。また、食品衛生責任者の配置が必要。 |
| 取得にかかる時間の目安 | 申請から許可まで通常1〜2週間程度。ただし、施設工事や改善指摘があった場合はさらに延びることがある。 |
店舗を出店する場合だけでなく、イベント出店時やキッチンカーで開業する場合は、出店する場所の保健所でそれぞれ飲食店営業許可を取得しなければなりません。
申請時には、食品衛生責任者の選任・届出が必要になるため、先に食品衛生責任者資格を取得しておくとスムーズに申請できます。
酒類販売業免許
種類販売業免許は、一般的な居酒屋でグラス・ジョッキ類で酒類を提供する場合には不要の資格です。ただし、テイクアウトや通販など、酒類の持ち帰り販売を行う場合には、取得が必須となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必須の理由 | 酒税法に基づき、酒類を小売販売(持ち帰り販売)する場合には「酒類販売業免許」が必要となるため。無免許での販売は法令違反となり、罰則が科される。 |
| 取得方法 | 営業所所在地を管轄する税務署へ申請書と必要書類(販売計画書、店舗図面、住民票、登記簿謄本など)を提出。審査の上、基準を満たせば免許が交付される。 |
| 取得費用 | 申請手数料は免許区分により異なり、一般酒類小売業免許は約30,000円程度。その他、書類取得や店舗改装にかかる費用は別途必要。 |
| 取得要件 | 欠格事由(過去の免許取消、酒税法違反など)がないこと。販売管理体制が整っていること、適正な保管設備があること、販売需要がある地域であること。 |
| 取得にかかる時間の目安 | 申請から免許交付まで通常2〜3か月程度。審査内容や申請書類の不備によってはさらに長期化する場合がある。 |
居酒屋開業時に酒類販売業免許が必要になるのは、以下のようなケースです。
- ボトルキープした酒を持ち帰らせる
- 家庭用に酒類を販売する(テイクアウト販売を含む)
- 酒を通販・宅配で販売する
これらのいずれかに該当する場合は、酒類販売業免許(一般酒類小売業免許)が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業届出
深夜種類提供飲食店営業届出も、居酒屋の中で一部の業態において、申請が必須となる届出です。具体的には、深夜0時(午前0時)以降に酒類を提供する、「飲酒を主目的とした飲食店」が対象となります。
深夜0時(午前0時)までに閉店する居酒屋の場合は、届出る必要はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必須の理由 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、深夜0時(午前0時)以降に酒類を提供して営業する飲食店は届出が必要。対象は、バー・居酒屋・スナックなど飲酒を主目的とした飲食店。 |
| 取得方法 | 営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)に届出書および必要書類(店舗平面図、設備図、賃貸契約書の写し、営業開始予定日を記載した書類など)を提出。営業開始の10日前までに届出を行う必要がある。 |
| 取得費用 | 手数料は不要。ただし、図面作成費用や契約書取得費用が発生する場合がある。 |
| 取得要件 | 対象となる営業形態であること(深夜0時以降に酒類提供を行う飲食店)。欠格事由(過去の法令違反や免許取消など)がないこと。防音・照明・構造等が法令基準に適合していること。 |
| 取得にかかる時間の目安 | 届出自体は即日完了するが、提出期限は営業開始の10日前までとされている。事前準備(図面作成・必要書類の用意)を含めると1〜2週間程度かかるのが一般的。 |
営業を開始する10日前までに申請が必要になるため、必要書類や店舗の図面などは早めに準備しておきましょう。
居酒屋開業に調理師免許・資格は必要?
居酒屋開業時に、調理師免許(調理師資格)は必ずしも必要ありません。取得していなくても、居酒屋を開業したり、調理に携わったりすることは可能です。
調理師免許の資格がなくても飲食店の開業は可能ですが、取得していると食材の調理や衛生面の対策に関する知識・スキルを有していることを証明できます。
調理師免許は、受験資格として「2年以上の調理業務経験」が挙げられているため、取得に2年以上を要する点に注意が必要です。
居酒屋開業時に取得しておくと便利な資格

居酒屋開業時に取得しておくと便利な資格は、以下のとおりです。
- 調理師免許
- ソムリエ(ワイン・野菜・ビール)
- カクテル検定
それぞれ、具体的にどのような利便性があるのか、活用シーンの例とともに解説します。
調理師免許
居酒屋開業時に取得しておくと便利な資格として、調理師免許が挙げられます。調理師免許を取得していると、食材の調理方法や衛生管理の知識・スキルを有していることを証明できるため、顧客からの信頼を得やすくなる点がメリットです。
また、調理師免許所持者は食品衛生責任者資格取得時に受講が必要な講習を免除されるため、すぐに申請して取得できる強みもあります。
例えば、開業予定までに数年単位で時間があり、自己資金を貯めながら資格を取得していきたい、と考えているのであれば調理師免許の取得を視野に入れてみるのも良いでしょう。
ソムリエ(ワイン・野菜・ビール)
ソムリエ資格も、居酒屋開業時に取得しておくと便利な資格の1つです。ソムリエといえば、ワインのイメージをもつ方も多いでしょう。実はワイン以外にも、野菜ソムリエやビールソムリエなど、さまざまな種類の資格があります。
それぞれに専門知識を有していることを証明できる民間資格で、テイスティング・利き酒が試験科目に含まれている場合があるのも特徴です。
最適な調理方法や、料理とワイン・ビールなどのマリアージュ(相性の良い組み合わせ)に関する知識も身に付きます。
カクテル検定
カクテル検定も、居酒屋開業時に取得しておくと便利な資格です。カクテルに関する基礎知識のほか、カクテルづくりの実技試験も実施されます。
カクテルに使用するお酒の酒類に関する知識に加え、バーでのマナーなども身に付けられる点が特徴です。
カクテルに使用する酒類の知識が深まるため、提供するドリンクメニューの開発や、マッチする料理の開発にも活用できます。
居酒屋開業時に必要な届出・許認可一覧
居酒屋開業時に必要な届出・許認可は、以下のとおりです。
| 届出の種類 | 提出場所 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 開業届(個人事業主の開業廃業等届出書) | 出店場所管轄の税務署 | 開業から1カ月以内 |
| 飲食店営業許可申請 | 出店場所管轄の保健所 | 店舗完成の10日前まで |
| 防火対象物使用開始届 | 出店場所管轄の消防署 | 建物の使用を開始する7日前まで |
| 火を使用する設備等の設置届 | 出店場所管轄の消防署 | 建物の使用を開始する7日前まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 出店場所管轄の税務署 | 開業から2カ月以内 |
| 給与支払事務所の開設届 | 出店場所管轄の税務署 | 給与支払事務所を開設してから1カ月以内 |
| 社会保険加入手続き | 日本年金機構 | 開業後すぐ |
| 雇用保険の加入手続き | 公共職業安定所 | 従業員の雇用開始から10日以内 |
| 労災保険の加入手続き | 労働基準監督署 | 雇用開始翌日から10日以内 |
| 食品衛生管理者の届出(※要資格) | 出店場所管轄の保健所 | 管理者設置から15日以内 |
| 防火・防災管理者選任届(※要資格) | 出店場所管轄の消防署 | 開業まで |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 出店場所管轄の警察署 | 開業の10日前まで(深夜0時以降も営業する場合) |
| 生食用食材の提供届出 | 出店場所管轄の保健所 | 提供開始前(許可・基準適合確認後) |
| 喫煙専用室設置届出 | 出店場所管轄の保健所または自治体の担当部署 | 設置工事完了前まで |
| 屋外広告物許可 | 店舗所在地を管轄する自治体(都市計画・建築指導課など) | 看板設置前(申請・許可取得後に設置可能) |
上記の許認可や届出は、提供するドリンク・料理、業態によっては不要なものもあります。自店舗の業態や提供する飲食物に応じて、必要なものを必要なタイミングで提出しましょう。
見落としを防ぐためにも、開業準備の段階でリスト化しておくと安心です。
居酒屋開業時に必要な資金の目安

居酒屋開業に必要な開業資金の目安は、約700万円~1,500万円です。店舗の規模や業態によっても異なるため、目安金額よりも少ない資金で開業できる場合もあれば、超える場合もあります。
居酒屋開業にかかる資金は、全額自己資金でなくても必要な開業資金の30%~40%程度あれば、創業融資を受けて開業することが可能です。
ただし、自己資金ゼロで居酒屋を開業するのは難しいでしょう。居酒屋開業にかかる資金の目安や、費用を抑えて開業するポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:居酒屋開業資金の目安はいくら?自己資金の金額や準備方法と開業費用の抑え方
居酒屋開業までの準備の流れ
居酒屋開業までの準備は、以下の流れで進めていきましょう。
- 店舗やメニューのコンセプトを設計する
- 事業計画書を作成する
- 自己資金を貯める
- 融資申請手続きを行う
- 人流データ分析や商圏分析で出店場所のデータ収集を行う
- 不動産屋で店舗用の物件を探す
- コンセプトに合わせて料理やメニューを開発する
- 店舗物件を契約する
- 店舗の内装工事・外装工事を行う
- 厨房設備を選定して購入する
- 必要な什器や備品類を揃える
- 必要な届出・許認可申請を行う
- 店舗スタッフの採用・教育を行う
- チラシ配布やポスティングで開業を宣伝する
- プレオープンで業務オペレーションを実践する
- 業務オペレーションを改善する
- 開業する
居酒屋開業に向けた準備期間は、開業日から起算して1年前を目安に着手し始めることをおすすめします。最低でも、半年は必要になると考えておきましょう。
また、自己資金の貯蓄に関しては、数年単位の準備期間が必要になります。資金の準備に時間がかかるため、資金を準備するのと並行して必要資格を取得しておけば、スムーズに開業準備に取り掛かれます。
参考記事:居酒屋を開業するために必要なものとは?自己資金の目安と必須資格・準備の流れを紹介
まとめ
居酒屋を開業するには、開業までに取得しておかなければならない資格があることに注意が必要です。比較的すぐに取得できる資格ではあるものの、開業準備に追われる中で取得するのは時間に追われる要因となります。
そのため、自己資金の貯蓄を進めている段階で資格も取得しておけば、開業準備に専念できるので、早めの取得がおすすめです。


