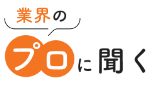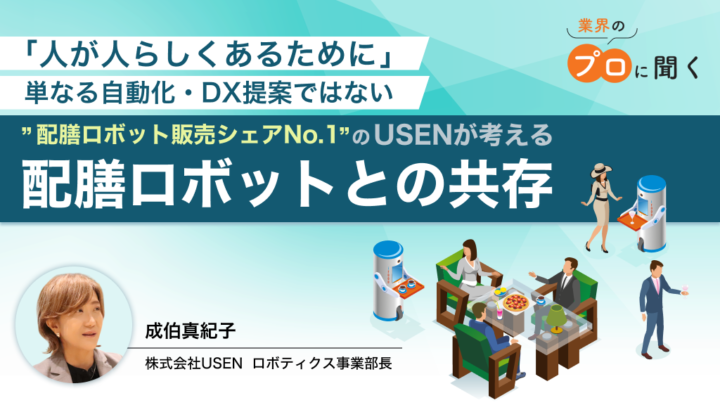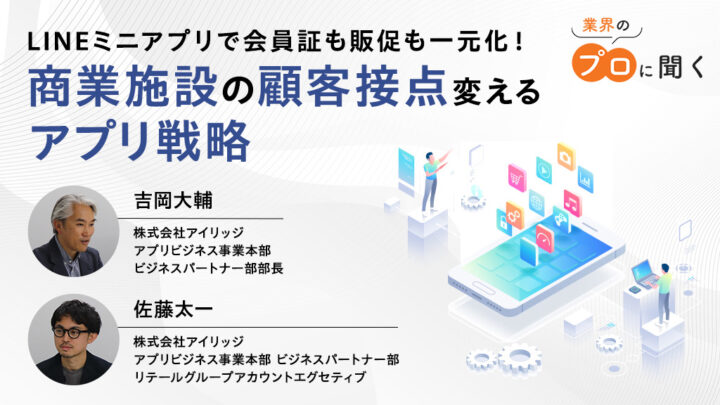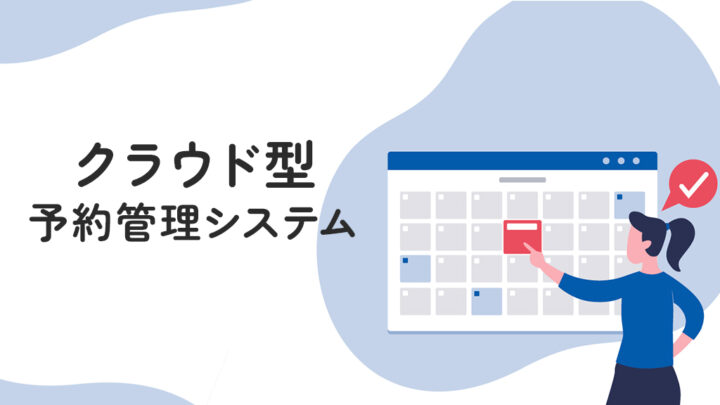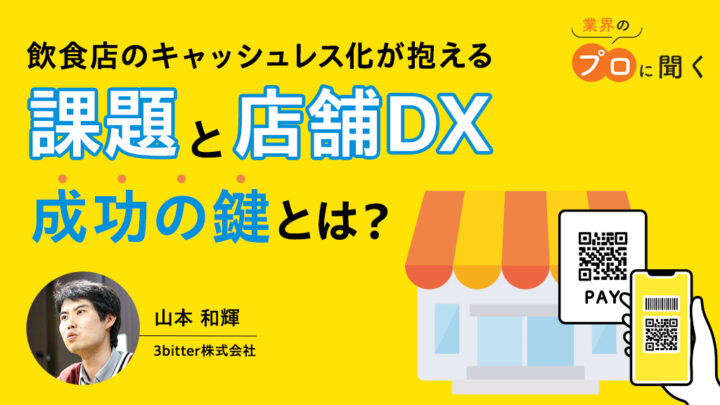
ABOUT
ビズカンとは
「店舗ビジネスをラクにできる」をテーマにした、店舗・施設ビジネス特化型の比較サイトです。
Bizcanは「ビジネス(Biz)」と「できる(can)」という言葉の組み合わせで生まれました。
あらゆる店舗・施設ビジネスを対象に、直面するさまざまな課題に対して解決策を提供し、ビジネスを成功に導くための情報とサービスを提供していきます。
Bizcanを通して、課題解決の方法を探すのも”ラク”に、店舗の経営も”ラク”になっていただければと考えています。
Bizcanは「ビジネス(Biz)」と「できる(can)」という言葉の組み合わせで生まれました。
あらゆる店舗・施設ビジネスを対象に、直面するさまざまな課題に対して解決策を提供し、ビジネスを成功に導くための情報とサービスを提供していきます。
Bizcanを通して、課題解決の方法を探すのも”ラク”に、店舗の経営も”ラク”になっていただければと考えています。