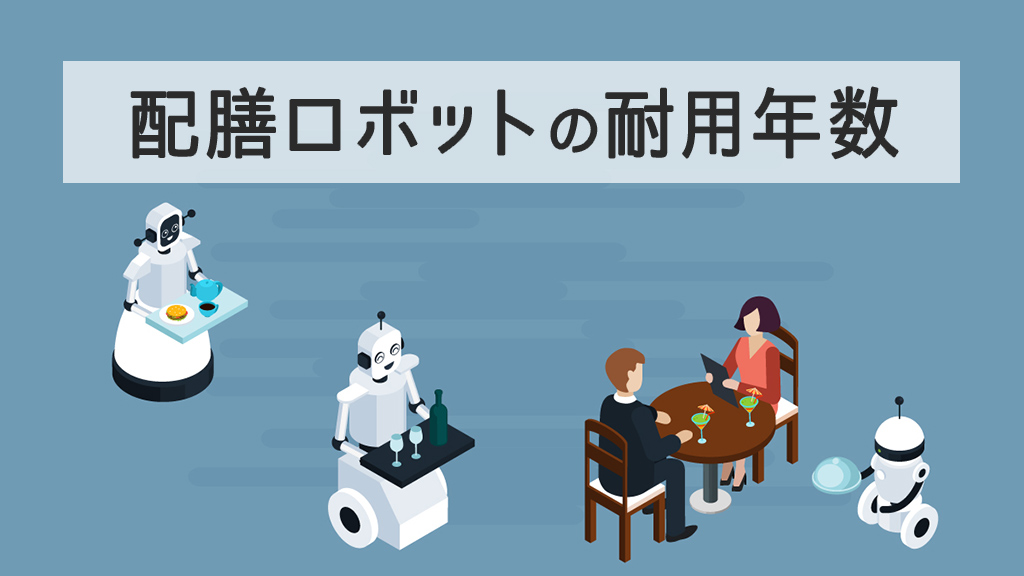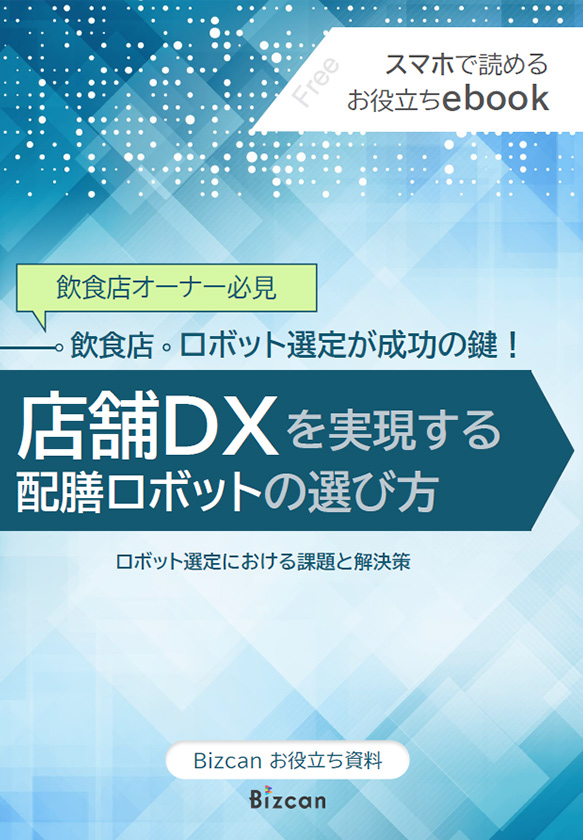配膳ロボットの耐用年数についてご存じでしょうか?機能や価格についてはある程度リサーチが進んだものの、実際どの程度の期間運用可能か分からない、という方もいらっしゃるでしょう。最大限配膳ロボットを有効活用するには、耐用年数について理解しておくことも重要です。そこで本記事では、配膳ロボットの耐用年数や費用対効果、保全活動などについて解説していきます。
配膳ロボットの耐用年数は?
 配膳ロボットの耐用年数は、メーカーやモデルによって異なります。
配膳ロボットの耐用年数は、メーカーやモデルによって異なります。
たとえば、タニコーの手掛ける配膳ロボット「PEANUT」は、耐用年数を5年としています。そのため、配膳ロボットの導入を検討する際は、事前に耐用年数についても確認しておくのが無難です。
できるだけ長く使用したい場合は、各メーカーの製品説明を確認し、耐用年数の長いモデルを選定するのも一つの手といえるでしょう。
導入に見合うかどうかの検討材料として、配膳ロボットの耐用年数について把握しておくことは重要です。
配膳ロボットの費用対効果は?
 本項では、配膳ロボットの費用対効果について解説します。
本項では、配膳ロボットの費用対効果について解説します。
配膳ロボットを時給換算すると?
配膳ロボットの費用対効果について考えるうえで重要となるのが、配膳ロボットを時給換算する考え方です。ここでは、配膳ロボットを時給に換算していきましょう。
月額費用の算出方法については、「本体価格÷耐用年数=月額費用」で算出可能です。上記で算出した月額費用をもとに、「月額費用÷営業時間/月=時給」で時給を求めることができます。
ここで算出した配膳ロボットの時給をもとに、費用対効果について判断する材料にすることができます。
配膳ロボットは決して安い買い物ではありません。コストに見合うだけの働きが期待できるかどうか、事前の見定めは不可欠です。
配膳ロボットの費用対効果
気になる配膳ロボットの費用対効果についてですが、結論からいえば、配膳ロボット一台で、スタッフ一人分の働きにすることは難しいと言わざるを得ません。
しかしながら、配膳ロボットは配膳・下膳業務を肩代わりできるため、その分の人件費を浮かせることはできます。たとえば、ホール業務にスタッフ1人、調理に1人割いていた場合、配膳ロボットを導入することで、ホール業務のスタッフを減らしても店舗オペレーションを回すことが可能になります。
そのため、費用対効果の結論としては、低い時給で一部業務を肩代わり可能な配膳ロボットの費用対効果は、高いといえます。
配膳ロボットの導入を検討する際は、おおよその概算でコストパフォーマンスを算出してみるとよいでしょう。
配膳ロボットの耐用年数を伸ばすために重要なポイントとは?
 本項では、配膳ロボットをできるだけ長く利用するために重要となる2つのポイントについて解説します。
本項では、配膳ロボットをできるだけ長く利用するために重要となる2つのポイントについて解説します。
ポイント①:事後保全
何らかのトラブルが起きた後に配膳ロボットの保全活動を行うことを、「事後保全」と呼びます。
たとえば、配膳ロボットの挙動や音に違和感を覚えたときは、事後保全のタイミングといえます。無理して運用を続けるのではなく、一旦配膳ロボットの電源を落とし、様子を見つつメーカーや修理業者に修理を依頼しましょう。
動けているから問題がないと判断するのではなく、違和感があったタイミングで保全活動を行うことが重要です。
ポイント②:予防保全
事後保全とは異なり、配膳ロボットの好不調に関わらず保全活動を行い、故障やトラブルを予防することを「予防保全」と呼びます。
予防保全を行うことで、店舗スタッフでは気づけなかった配膳ロボットのトラブルを発見し、対処できる点が強みです。
なお、予防保全には時間基準保全と状態基準保全の2種類に分類されます。あらかじめ決められた期間ごとに保全活動を行うことを時間基準保全と呼び、何らかの異常が確認できたタイミングで保全活動を行うことを状態基準保全と呼びます。
いずれにせよ、早めの保全活動を行うことで、より長く配膳ロボットのパフォーマンスを維持することに繋がるでしょう。
重要となるのは事後・予後の保全です。しっかりとケアしていくことで、配膳ロボットを不具合なく活用できます。
まとめ
本記事では、配膳ロボットの耐用年数、費用対効果やできるだけ長く運用していくために重要なポイントを解説しました。
配膳ロボットは一台数百万と、相応のコストがかかります。そのため、まずは導入段階で配膳ロボットの費用対効果について分析を行いましょう。また、導入後はしっかりと耐用年数分運用していくためにも、日頃の保全やサポートの活用が重要となります。
本記事で紹介した内容を参考に、配膳ロボットを最大限有効活用できるようにしていきましょう。