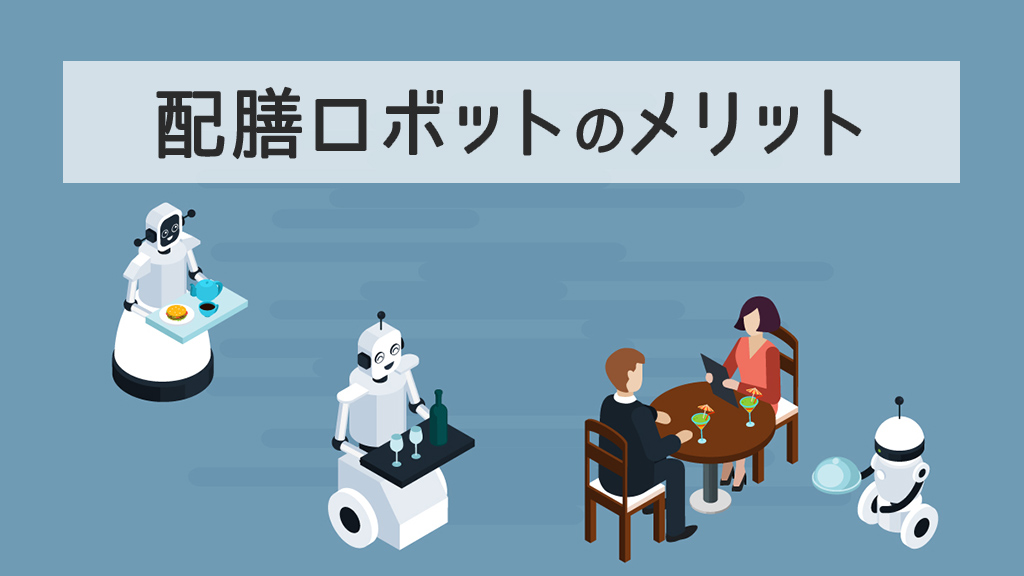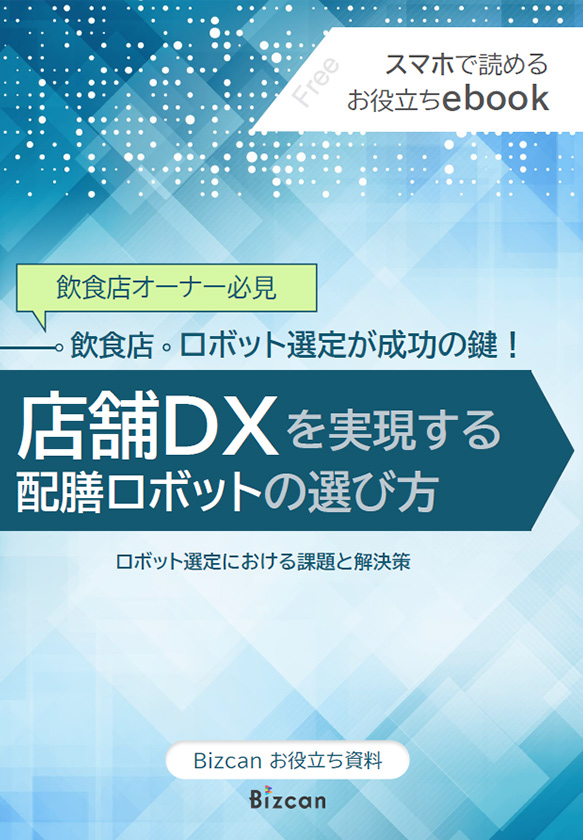近年注目を集めている配膳ロボットですが、実際に導入することでどのようなメリットを得ることができるのでしょうか。また、デメリットはあるのでしょうか。導入を検討するにあたって、メリット・デメリットの部分を明確にしておくことは重要です。本記事では、配膳ロボット導入のメリット・デメリットを中心に解説していきます。
配膳ロボット導入店舗が増えている背景とは?
 本項では、配膳ロボットの導入店舗が近年増えている背景について解説します。
本項では、配膳ロボットの導入店舗が近年増えている背景について解説します。
飲食業界の人手不足
配膳ロボットの導入が近年急速に進みつつある背景に、飲食業界の人手不足という問題があります。慢性的な人手不足に悩まされている飲食店は多く、業務が円滑に回らない、営業時間を短縮せざるを得ないといった問題に繋がっています。
上記の問題に対する一つの解決策として、配膳業務を自動化し、省人化できる配膳ロボットの導入が注目され、実際に導入店舗も増加し続けています。
アフターコロナ下での変化
新型コロナウイルスの流行という時代の大きな変化を経て、現在はアフターコロナと呼ばれる時代に突入したといえるでしょう。そのなかで、衛生面を考えての「非接触」を求める層は少なくありません。
上記のような需要がある中で、飲食店の配膳業務を対人接触なしでこなすことのできる配膳ロボットは、時代の流れにマッチするツールの一つといえます。
DX推進の流れ
さまざまな業界で進んでいるDX推進の流れですが、飲食業界においてもそれは例外ではありません。さまざまなツールやシステムを導入することで、飲食店においても業務効率化、生産性の向上に繋げようという流れがあります。
食事の配膳・下膳業務を自動化し、効率的に進めることができる配膳ロボットの導入は、飲食業界においてDX推進の流れの一つと捉えることが可能です。
本項で紹介したように、さまざまな背景から、飲食業界において配膳ロボット導入店舗が増えています。
配膳ロボット導入によるメリット
 本項では、配膳ロボット導入によるメリットについて解説します。
本項では、配膳ロボット導入によるメリットについて解説します。
業務効率化
配膳ロボットを導入することにより、店舗における業務の効率化に繋がります。
これは「配膳業務の効率化」という点のみならず、店舗業務全体の効率化にも繋がります。たとえば、配膳ロボットの導入により配膳業務を行うスタッフが必要なくなることで、接客サービスや調理など、その他店舗業務の人員を厚くすることができます。
これにより、配膳業務以外の業務領域でも円滑に業務進行できるようになり、全体の効率化に繋げることが可能です。
従業員の負担減
慢性的な人手不足に悩む飲食店において、従業員に過度な業務負荷がかかってしまっている、という店舗も少なくないでしょう。中には、一人で調理から配膳をこなすなど、複数の業務領域をクロスオーバーしてこなしている店舗もあるはず。
配膳ロボットの導入により、従業員の負担減も期待できる効果の一つです。配膳・下膳業務に人を割く必要がなくなります。結果として従業員はその他の業務に集中すればよくなるため、かかっていた業務負担を軽減することに繋がります。
非接触の実現
前述したように、アフターコロナの現在、飲食店において非接触での提供を望む層は珍しくないでしょう。その点、無人で料理・飲み物を提供できる配膳ロボットの導入は、非接触を実現できるツールの一つです。
配膳ロボットを運用し、非接触で提供ができるようになれば、「衛生面に配慮している店舗」というポジティブなイメージを食事客に与えることができる点もメリットといえます。
配膳ロボットを導入することで、業務効率や衛生面でプラスの効果を得ることができます。
配膳ロボット導入のデメリットとは?
 一方、配膳ロボットを導入することで、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
一方、配膳ロボットを導入することで、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
導入コストがかかる
配膳ロボット導入におけるデメリットとして、やはりコスト面は見逃せません。たとえば配膳ロボットを購入する場合、最低でも100万円以上の初期コストが必要です。
これは予算規模の大きくない小規模な飲食店にとって、かなり大きなハードルといえます。レンタル・リースという手段もありますが、コストパフォーマンスの算出が難しい部分もあるでしょう。
事故のリスクがある
便利な配膳ロボットではありますが、運用する中で事故に繋がる恐れもあります。たとえば、食事客と衝突してしまう、配膳ロボットが転倒して食器を割ってしまうなど、想定される事故の種類はさまざまです。
事故が発生し、食事客のケガなどに繋がってしまうケースを避けるためにも、まずは店舗内でどのように配膳ロボットを安全に運用していくか、事前に共通認識を持つようにしましょう。
導入しづらい飲食店もある
店舗の特徴やレイアウトによっては、配膳ロボットの運用が難しい場合もあります。
たとえばバーなど、カウンター席が多い飲食店では、配膳ロボットによる配膳がむしろ非効率の原因になってしまう可能性があります。配膳ロボットを効果的に運用できるかどうか、自店の環境や特徴と照らし合わせつつ、事前に検討しておくことが重要です。
配膳ロボットの導入に際しては、導入コストや事故のリスクなど、ポイントを事前におさえておきましょう。
配膳ロボットの導入を検討すべき店舗とは?
本項では、配膳ロボットの導入を検討すべき店舗の特徴について解説します。
人手不足を課題としている
慢性的な人手不足で業務に影響が出ている飲食店の場合、配膳ロボットの導入を検討すべきといえるでしょう。
配膳ロボットの導入を行うことで配膳業務を完全に省人化することができます。これにより、人手を増やさずとも、円滑な業務進行が可能になる場合もあるでしょう。
人手不足を課題としており、実際の店舗業務に悪影響が出ている場合は、配膳ロボットの導入を解決策にできるはずです。
店舗規模が大きい
店舗規模が大きい場合、かなり多くの配膳業務が発生します。ファミリー層が中心の店舗ともなれば、その傾向はより顕著でしょう。
このような場合、一度に多くの料理・飲み物を配膳できる配膳ロボットの導入は店舗業務の効率化という意味で有効です。
自店の規模が広く、配膳業務に時間がかかって回転率に問題が生じているなど、課題を感じている場合は配膳ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
サービスの質を向上させたい
料理の提供に時間がかかってしまうなど、現在のサービスの質に課題を感じている飲食店でも、配膳ロボットの導入は有効です。
配膳ロボットは調理の手助けができるツールではありませんが、その分スムーズな配膳を実現し、調理、配膳、下膳という一連の流れをブラッシュアップすることは可能です。
配膳業務が円滑になることで顧客からのクレームなども減り、良質なサービスの提供にも繋がるでしょう。
特定の条件に一致する場合、配膳ロボットの導入がマッチする場合もあります。”
まとめ
本記事では、配膳ロボット導入が進んでいる背景やメリット・デメリット、導入を検討すべき店舗の特徴について解説しました。配膳ロボットの導入には多くのメリットがありますが、一方で事前に把握しておくべき注意点もあります。本記事の内容を参考に、配膳ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。