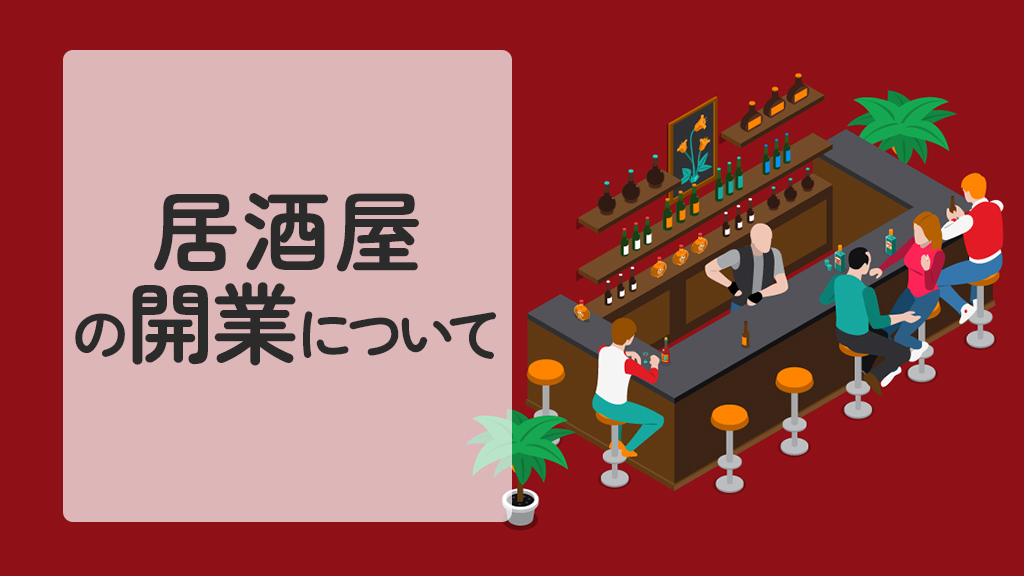居酒屋を開業する際、資金や設備・資格・許認可など、さまざまな準備が必要になります。
準備すべきことが膨大にある中で、抜け漏れを防ぐためには、具体的になにが必要でどのようなタイミングで準備に着手すれば良いのか、事前に把握しておくことが大切です。
本記事では、居酒屋を開業する際に必要なものや準備の大まかな流れと、事前に把握しておきたい資金や資格・許認可申請の情報について、詳しく解説します。
居酒屋を開業するために必要なもの

居酒屋を開業する際、準備が必要なものは大まかに分けると以下の項目です。
- 自己資金・開業資金
- 資格取得・申請
- 許認可申請・取得
- 店舗物件・設備・備品類
- 従業員(調理担当・接客担当)
- 宣伝・集客手段
店舗の規模や立地条件によって、必要な資金額や物件・設備の選定内容は左右されます。自店舗にどのような準備が必要なのかを判断しながら、着実に開業へ向けた準備を進めていくことが大切です。
居酒屋を開業するまでの準備の流れ
居酒屋を開業するまでの準備は、以下の流れに沿って進めるケースが一般的です。
- 店舗やメニューのコンセプトを設計する
- 事業計画書を作成する
- 自己資金を貯める
- 融資申請手続きを行う
- 人流データ分析や商圏分析で出店場所のデータ収集を行う
- 不動産屋で店舗用の物件を探す
- コンセプトに合わせて料理やメニューを開発する
- 店舗物件を契約する
- 店舗の内装工事・外装工事を行う
- 厨房設備を選定して購入する
- 必要な什器や備品類を揃える
- 必要な届出・許認可申請を行う
- 店舗スタッフの採用・教育を行う
- チラシ配布やポスティングで開業を宣伝する
- プレオープンで業務オペレーションを実践する
- 業務オペレーションを改善する
- 開業する
順番に多少の前後はあれど、基本的な準備の進め方は変わりません。ただし、選定した設備の導入に不備が出たり、許認可申請に不足が出たりと、突発的な対応が必要になる場面もあります。
そのため、準備を進めるときは、期限や時間・スケジュールに余裕をもって着手すると良いでしょう。
参考記事:飲食店開業までの流れと必要資格|開業準備はいつ始めるのがベスト?
居酒屋開業に必要な自己資金・開業資金の目安

居酒屋を開業する際に必要な自己資金の目安は、300万円~1,200万円です。居酒屋の開業資金は、トータルで約500万円~1,500万円必要になります。スケルトン物件ではなく、内装や設備が残った居抜き物件を活用すると、初期費用が削減できるでしょう。
資金計画的に、居酒屋の開業にかかる費用を全額自己資金でまかなうことが難しい場合、融資を受けて資金調達を行うケースが一般的です。初めて開業する場合、基本的には実績がなくても利用できる「日本政策金融公庫の創業融資」を利用します。銀行の融資は、担保や取引実績がないと融資審査に通りにくい傾向があるためです。
日本政策金融公庫の創業融資は、自己資金ゼロでも申請できます。しかし、自己資金ゼロで融資審査に申し込むと、審査落ちして融資を受けられなくなる可能性が高くなるので注意が必要です。一般的には、融資金額の20%~30%程度の自己資金があれば、審査に通りやすいとされています。
参考記事:飲食店開業の資金はいくら必要?資金調達方法と自己資金の目安や補助金・助成金制度まとめ
居酒屋開業に必要な資格
居酒屋を開業する際、必ず取得しておかなければならないのは、以下2つの資格です。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
ここでは、それぞれの資格をどのようにして取得すれば良いのか、取得にかかる時間や取得が必須とされている理由について解説します。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は、食品を取り扱う際、配慮しなければならない衛生面に関する知識を証明する資格です。飲食関連の事業を経営する場合、必ず営業許可施設につき1人の配置が必要になります。
店舗をもたず、イベント出店やキッチンカーなどで食品を提供する場合も同様です。食品衛生責任者資格は、都道府県で定められている専用の講習会を受講し、確認試験をクリアすれば取得できます。
一般的には1日の講習を受講すれば取得できる資格ですが、オンライン受講の場合は複数日かかるケースもあるので、受講方法も検討しておきましょう。
防火管理者
防火管理者は、火災の発生を予防し、万が一火災が発生した際に、店内・施設内にいる人の避難誘導を行う専任者の資格です。
甲種と乙種の2種類の資格があり、店舗・施設の規模や収容人数、用途などによって必要な資格が異なります。
防火管理者は、店舗・施設全体の防火設備(火災報知器・消火器など)の設置・点検や、消防計画の作成などを行う役割です。収容人数が30人を超える建物では、必ず選任しなければなりません。
店舗が300㎡未満の小規模居酒屋を開業するのであれば、「乙種防火管理者」の資格が必要です。300㎡以上の場合は「甲種防火管理者」の資格を取得する必要があります。
参考記事:飲食店開業に必要な資格一覧|調理師免許の有無や届出の申請についても解説
居酒屋を開業するのに「調理師免許」は必要?
居酒屋を開業する際、調理師免許は必要ありません。調理師免許を取得していなくても、居酒屋を開業してオーナーとして働くだけでなく、食事の調理・提供に従事することも可能です。
一方で、取得していると調理に関する知識を有していることが証明でき、顧客からの信頼につながるメリットがあります。
また、調理師免許は、栄養士・製菓衛生師などの資格と同様に、取得しているだけで食品衛生責任者の資格を有している扱いになるのも特徴です。講習を受講することなく、食品衛生責任者として届出ができます。
居酒屋開業に必要な届出・申請
居酒屋開業に必要な届出・申請については、以下のとおりです。
| 届出の種類 | 提出場所 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 開業届(個人事業主の開業廃業など届出書) | 出店場所管轄の税務署 | 開業から1カ月以内 |
| 飲食店営業許可申請 | 出店場所管轄の保健所 | 店舗完成の10日前まで |
| 防火対象物使用開始届 | 出店場所管轄の消防署 | 建物の使用を開始する7日前まで |
| 火を使用する設備等の設置届 | 出店場所管轄の消防署 | 建物の使用を開始する7日前まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 出店場所管轄の税務署 | 開業から2カ月以内 |
| 給与支払事務所の開設届 | 出店場所管轄の税務署 | 給与支払事務所を開設してから1カ月以内 |
| 社会保険加入手続き | 日本年金機構 | 開業後すぐ |
| 雇用保険の加入手続き | 公共職業安定所 | 従業員の雇用開始から10日以内 |
| 労災保険の加入手続き | 労働基準監督署 | 雇用開始翌日から10日以内 |
| 食品衛生管理者の届出※要資格 | 出店場所管轄の保健所 | 管理者設置から15日以内 |
| 防火・防災管理者選任届※要資格 | 出店場所管轄の消防署 | 開業まで |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 出店場所管轄の警察署 | 開業の10日前まで※深夜0時以降も営業する場合 |
これらは、業種・業態によって届出・申請が必要なものもあれば、必要ないものもあるので、自店舗に該当するものをあらかじめリストアップしておくと良いでしょう。
提出期限がそれぞれ異なるため、期限超過にも注意が必要です。可能な限り早めに提出しておきましょう。
参考記事:飲食店開業時のチェックリスト!準備の見落としを防ぐポイントを解説
居酒屋開業・経営時に利用できる補助金・助成金制度
居酒屋を開業する際、自己資金や融資だけで初期費用をまかなうと、開業後に返済に追われて収益が手元に残らず、運転資金が確保できなくなります。
そのような状況を回避するには、居酒屋開業時や経営中に利用できる補助金・助成金制度を利用して、初期費用の負担を軽減する方法が効果的です。
居酒屋を開業する際や運転資金として、利用できる補助金・助成金制度には以下のものが挙げられます。
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金
- 働き方改革推進助成金
- キャリアアップ助成金
それぞれに、設備投資や従業員の賃金引上げなど、適用される要件が異なります。詳しくは、以下の記事でも解説していますので、こちらもぜひ参考にしてください。
参考記事:【2025年最新】飲食店開業に利用できる補助金・助成金制度まとめ!自治体独自の制度も紹介
まとめ
居酒屋を開業する際、どのような店舗にしようか、どのようなメニューやお酒を提供しようかなど、店舗のコンセプト設計を検討することはとても大切です。
しかし、コンセプトを実現するためにはなにが必要か、どのような顧客層をターゲットにすれば良いかなど、居酒屋経営者としてマーケティング方法も検討していかなければなりません。
居酒屋開業に向けて、自分の理想とする店舗を作り上げることに終始するのではなく、具体的に収益を上げられる店舗の実現に向けて着実に準備を進めていきましょう。