近年導入が進むクラウドカメラですが、耐用年数はどの程度なのでしょうか?本記事では、クラウドカメラの耐用年数や耐用年数が短くなってしまう原因、長く活用するための秘訣などを解説します。
クラウドカメラとは?
 本項では、クラウドカメラの概要について解説します。
本項では、クラウドカメラの概要について解説します。
クラウドカメラとは、通常の防犯カメラとは異なり、クラウド上で映像の管理・保存などを行える防犯カメラです。
通常の防犯カメラでは外付けのHDDなどの録画機器を取り付ける必要がありますが、クラウドカメラは本体が撮影した映像をそのまま接続されたインターネット上のクラウドに保存できます。
クラウドカメラを導入することにより、監視業務の改善に役立てることができます。
クラウドカメラの活用例や導入メリットは以下の記事で解説していますので、チェックしてみてください。
関連記事:クラウドカメラとは?導入メリットや注意点、実際の活用例について解説
クラウドカメラの耐用年数は?
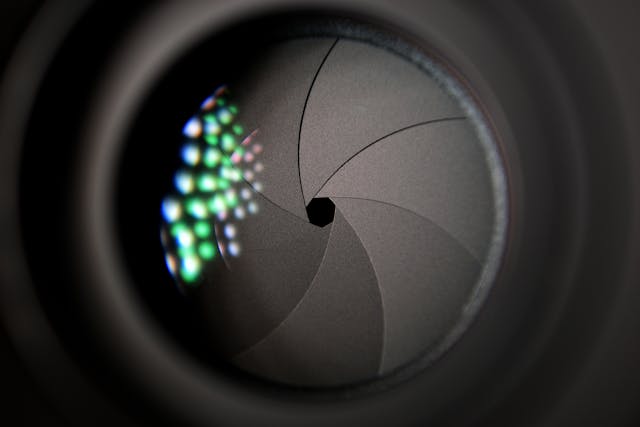 クラウドカメラの耐用年数は、一般的に6年程度とされています。そのため、一度導入した場合は約6年程度、運用する想定をしておくのが無難です。
クラウドカメラの耐用年数は、一般的に6年程度とされています。そのため、一度導入した場合は約6年程度、運用する想定をしておくのが無難です。
ただし、耐用年数はメーカーや製品ごとに異なる点、不具合や故障が起きた場合は買い替えが必要になる可能性がある点には注意してください。
クラウドカメラの導入検討時は、耐用年数も比較検討の材料にしましょう。
クラウドカメラと通常の防犯カメラの耐用年数に違いはある?
そもそも、クラウドカメラと防犯カメラには耐用年数に違いはあるのでしょうか。本項では、クラウドカメラと通常の防犯カメラの耐用年数にはどのようなポイントで違いがあらわれるのか、要素別に解説していきます。
録画方式の違い
クラウドカメラは、映像をローカルのHDDなどに保存せず、インターネットを通じてクラウドに直接保存する仕組みです。この仕組み上、録画機器の物理的な故障やHDDの寿命によるトラブルが軽減され、結果としてシステム全体の耐用年数が安定しやすくなるという特徴があります。
一方、従来型の防犯カメラは録画装置とセットで使用されることが多く、HDDなどの記録媒体が3〜5年で劣化するため、記録装置側の故障がカメラ運用全体の寿命を左右するリスクが高まります。このように、録画方式の違いが、実際の運用期間にも差を生む要因となっています。
設置・運用環境の違い
クラウドカメラは、インターネットを介して遠隔地から状態の確認や映像チェックが可能な製品が多く、異常や故障の兆候に早期に気づきやすい点が強みです。管理者が定期点検をリモートで行えるため、メンテナンスの効率が高く、耐用年数を引き延ばす要因となります。
一方、通常の防犯カメラでは、現地での目視確認や直接操作が基本となり、トラブルに気づくまでに時間がかかることがあります。とくに遠隔地に設置されたカメラでは、メンテナンスが後手になりやすく、知らないうちに劣化が進んでいるというリスクもあるでしょう。
なお、屋外で利用するタイプのクラウドカメラについては以下の記事でも解説しています。
関連記事:クラウドカメラは屋外でも利用できる?活用シーンや注意点も解説
保守体制の違い
クラウドカメラは、メーカーやサービス提供者によって、定期的なファームウェアアップデートやセキュリティパッチが自動的に適用される製品が増えています。これにより、システムの安定性が保たれ、長期にわたって安心して利用しやすい傾向があるといえるでしょう。
また、保守契約により、故障時の対応やリモート診断などが整備されていることも多く、結果的に機器の寿命を延ばすことにもつながります。一方、従来型のカメラはアップデート機能がない場合も多く、ハード面の劣化だけでなく、ソフト面の陳腐化が買い替えの早期化につながるケースも見られます。
クラウドカメラの耐用年数が短くなってしまう原因
本項では、クラウドカメラの耐用年数が短くなってしまう原因について解説します。
カメラの点検を怠ってしまう
クラウドカメラは6年程度の耐用年数で設計されているとはいえ、定期的な点検は不可欠です。定期的にメンテナンスを行ったうえで「6年程度」運用可能、というように捉えておきましょう。
クラウドカメラの点検を怠ってしまうと、知らぬ間に不具合や故障が生じていた場合に対応が遅れてしまい、耐用年数が短くなってしまう原因になり得ます。
そのため、決まった周期でクラウドカメラの点検を行うのは重要です。
LANケーブルを交換せずに使う
クラウドカメラはインターネット上のクラウドと接続されている必要があります。そのため、クラウドカメラ本体はLANケーブルと繋いでおかなければなりません。
しかしながら、LANケーブルは経年劣化によって機能不全に陥る消耗品です。LANケーブルを交換せず、ずっと接続したままにしていると、接続不良を起こし、運用に支障をきたす恐れがある点に注意しましょう。
設置環境が悪い
設置環境も、クラウドカメラの耐用年数を短くしてしまう要因の一つになり得ます。
たとえば、屋外の風に晒されやすい場所に設置して運用するなど、劣悪な環境下で運用を行っている場合、クラウドカメラの不具合や故障に繋がり、本来の耐用年数を迎える前に運用不可能な状態に陥ってしまう可能性もあります。
本項ではクラウドカメラの耐用年数が短くなる原因について解説しました。
クラウドカメラを長く運用する方法とは?
 本項では、できるだけ長くクラウドカメラを運用するための方法について解説します。
本項では、できるだけ長くクラウドカメラを運用するための方法について解説します。
カメラ本体の点検
クラウドカメラ本体の点検は周期的に行うよう注意しましょう。
本体の点検を定期的に実施することで、小さな不具合や故障に気づくきっかけになります。もし不具合があった場合には、すぐに修理に出し、状態を万全に保っておくことが重要です。
LANケーブルの点検
カメラ本体だけでなく、接続されるLANケーブルに関しても定期的に状態を確認し、劣化が見られた場合は交換を行うことをおすすめします。
特にLANケーブルの点検や交換は後回しになってしまいがちですが、問題なくクラウドカメラを運用していく上で不可欠なツールとなるため、状態を万全にしておいて損はありません。
もう何年もLANケーブルを交換していないという場合には、一度状態を確認し、交換を検討してみるのが無難です。
不具合を感じた際はメンテナンスに出す
日々クラウドカメラを運用する中で、不具合を感じることがあるかもしれません。たとえば映像が正常に撮影されていない、クラウドへの保存が上手くいかないなど、不具合の内容はさまざまです。
もしクラウドカメラの状態に違和感を覚えた際は、まずメーカーや修理業者へメンテナンスを依頼するのが無難です。早期に故障や不具合の改善を行うことで、長期的な運用に役立ちます。
本項ではクラウドカメラを長く運用する方法について解説しました。
クラウドカメラの買い替え・入れ替え時期の目安とは?
長く運用していても、耐用年数を迎えたときをはじめ、さまざまなタイミングでクラウドカメラの買い替え・入れ替えを行う必要性が生じます。では具体的にどのようなポイントで買い替え・入れ替えのタイミングを見極めればよいのでしょうか。本項で解説していきます。
映像の画質や処理速度に不満が出てきたら
カメラ自体が正常に稼働していても、年月の経過とともに映像品質や動作速度に不満を感じる場面が増えてくることがあります。
たとえば、映像が以前よりもぼやけて見える、再生時に遅延が発生する場合、経年劣化や内部ソフトウェアの限界を示している可能性が想定されるでしょう。特にクラウドカメラは、定点監視だけでなく、トラブル発見や証拠保全のための高画質が求められるため、映像品質の低下は業務上のリスクです。
こうした変化が顕著に現れてきた場合、買い替えを検討する時期に差し掛かっていると言えるでしょう。
ソフトウェア・アプリの更新に対応しなくなったら
クラウドカメラの多くは専用のアプリやソフトウェアを通じて操作・確認が必要です。長年使用していると、OSのアップデートやアプリ仕様の変更により、古い機種では最新機能に対応できなくなるケースがあります。
たとえば、アプリが起動しない、映像の確認に不具合が出るといった現象が発生した場合、ハード自体が使えていても実質的な運用は困難になるでしょう。こうした状態が続いた場合は、安全・快適な運用のためにも、新しい機種への移行を前向きに検討することが望まれます。
保証切れ・部品供給終了の案内が届いたら
メーカーから製品保証期間の終了や、部品供給終了のお知らせが届いた場合は、入れ替えのタイミングが近づいていると考えるのが妥当です。
クラウドカメラは精密機器でありながら24時間稼働を求められるため、万が一のトラブルに対する迅速なサポートが重要です。サポートが終了してしまうと、修理できない=買い替えが必須となる可能性が高くなります。
予防的な観点からも、こうしたお知らせを見逃さず、計画的なリプレイスを検討することが、トラブル回避に繋がります。
まとめ
本記事では、クラウドカメラの耐用年数や、耐用年数が短くなってしまう原因、長く運用する秘訣について解説しました。クラウドカメラの保守管理に配慮することで、耐用年数より前に故障してしまうといったトラブルの予防に繋がります。



